森本俊司「ディック・ブルーナ ミッフィーと歩いた60年」(2019、文春文庫) [本と雑誌]

ブルーナが「うさこちゃん」を描きはじめる以前、父親の会社でブックデザインを手掛けていたことはよく知られている(そうでもない?)が、さらにそれ以前の、生い立ちや経歴が紹介され(ドラ・ド・ヨングの「あらしの前」「あらしのあと」を連想する読者も多いだろう)、彼が作品の中で周到に暴力を遠ざけている理由の一端を知ることができる。また、父親とのあいだでさまざまな確執があったことを知る(他方で、彼とこどもたちとの関係は、とても良好だったようだが)。
また、絵本づくり以外のさまざまな取り組みについても紹介されているが、特に惹かれたのは、福祉やこどもの健康のためのポスターなどのデザインにも進んで取り組んできたことが紹介されている中、島根大学医学部付属病院小児センターの壁やドアにブルーナの絵が描かれている(本の中では、ごく小さな写真しか見ることができないが)ことで、やむをえず入院することになったこどもにとって、これがどれほど心の支えになるかと考えると本当にありがたい。思いつくのは簡単でも実行に移すことがむずかしい中、実現に向けて努力された多くの方がおられたことと思われ、つくづくありがたいことだと感じる。
なお本書は、その少なからぬ部分が著者による取材メモからなるため、どうしても著者が前景化してしまうのだけど、読者の多くは、著者ではなくディック・ブルーナのファンであろうから、そこはもう少し書き方の工夫があってもよかったように思う。
村上春樹「ヤクルト・スワローズ詩集」(「文學界」2019年8月号) [本と雑誌]

大久保孝治さんのブログ「フィールドノート」7月15日分を読んで、村上春樹がかつて同名の私家版を頒布していたものと勘違いし、「日本の古本屋」などで検索してしまった。そうではないのですね。勘違いに気づいて本屋に走り、まだ積んであった「文學界」8月号を入手する。
で、この小説(「ヤクルト・スワローズ詩集」というタイトルの小説です)なのだけど、あくまで小説の体裁をとりつつも、文藝春秋6月号「猫を棄てる」に続き、父親との確執に触れた部分がある。この部分は、もはや小説というより別の何かではないかと思わせるほどだ。
昨年7月11日の日経新聞夕刊に池田克彦さんが書かれていた「村上先生の思い出」と題するコラムで、甲陽学院の教師だった父親がどこかの予備校で、自分は入学の周旋等をしないことを説明し、「私には全く力はありません。現に、私の息子はこの学校の入試に落ちています。こんな私のところに挨拶に来られても何の意味もない」と言ったとあるので、これは随分ひどい話(そういう発言をする父親も、それを書いてしまう池田氏も、それを載せてしまう日経新聞も)だなあと思ったものだが、それから1年経って、これまで決して(記憶の限りでは)このことについて言及しなかった村上さんが立て続けに、父親との関係をとりあげた作品を発表したことに驚く。これは、村上さん自身が「自分の持ち時間」を意識されていることの現れなのかもしれず、すこし心配になる。
なお、もう1編の「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」も、村上さんらしい、胸がしめつけられるような、苦い余韻がのこる小説だった。こちらは小説らしい小説で、かつ、どこから読んでも村上さんの作品とわかる何かが充満している。
二冊の『自省録』(神谷美恵子訳,岩波文庫,1947/鈴木照男訳,講談社学術文庫,2006) [本と雑誌]

Eテレ「100分de名著」4月のテキストは、マルクス・アウレリウス『自省録』!
『自省録」は、わがオールタイムベスト10に入る本なので、この地味な哲学書を「100分de名著」が取り上げてくださったことに感謝。
テキストを読むと、この本の成り立ちについて、今まで知らなかったことも含めて解説されていて、ほうほうと納得。しかし、公開を前提としていなかった個人的手記に写本があって、それが16世紀になってから印刷(活版?木版?)された経緯が今一つよくわからない(16世紀までに、写本の所蔵先で広く使われていたとか、写本の写本がたくさん出回っていたということだろうか)。この点は、岩波文庫版でも明らかにされていない。
また、講師の専門からしてしょうがないのだろうけど、「自省録」のいろいろな部分について、アドラーも同様のことを言っていると紹介するのはどうなのだろう。事実そうなのだろうけど、自省録ファンの多くは、洵に申し訳ないが、アドラーの話を聞きたいわけではないのです。それに、後世の人が同様のことを言っているというなら、徒然草だって「自省録」と同様のことを言っているわけで。たとえば59段や85段などは、「兼好法師は『自省録』を読んでいたのかな?」と思ってしまうほどだ。
それはともかく、ここへきて「自省録」が本屋で平積みになっているのを見ると、少しでも多くの人がこの本を手に取ってくれたらと願わずにいられない。手元にある1冊目の『自省録』(写真左側)は、言わずと知れた岩波文庫版(神谷美恵子訳)であるが、これを本屋で入手してから、今月でちょうど40年になる(こう書くと、年齢が40歳以上であることがバレてしまうが、致し方ない)。この本を読む前と読んだ後で、自分の人生はすっかり変わってしまった(変わったわけではなく、もともとそういうメンタリティの持ち主だったから、この本に共感したとも考えられるが)。世界史の先生がタイトルを教えてくださった授業の様子とか、初めて手に取った本屋の棚とか、開いて読み始めた駅のホームとか、この本にまつわるさまざまな風景を、いまも鮮明に覚えている。また、就職して実家を出たとき荷物に加えた数少ない本の一冊でもある。
で、いい本だと言っておきながら、新訳が出ていることを知らなかったのも情けないのだけど、この機会に新訳(写真右側)も購入して、改めて両方に目を通してみる(本屋さん、なかなか商売上手です)。ひととおり最後まで読んでみたのだが、これは旧訳のほうが読みやすいといわざるを得ないのではないかなあ。例として、3章10節の冒頭と4章45節を挙げるとこんな感じ。以下引用。
(旧訳)
ほかのものは全部投げ捨ててただこれら少数のことを守れ。それと同時に記憶せよ、各人はただ現在、この一瞬間にすぎない現在のみを生きるのだということを。その他はすでに生きられてしまったか、もしくはまだ未知のものに属する。
(新訳)
されば、すべてを放下しただそれら僅かなことのみを堅持せよ。そしてなお合わせて銘記せよ――各人はただ束の間のこの現在のみを生きているのである。それ以外はすでに生き終えてしまったこと、ないしは、いまだ明らかならぬ不確定のことである。
(旧訳)
後に続いて来るものは前に来たものとつねに密接な関係を持っている。なぜならばこれは単にものを別々に取り上げて数えあげ、それがただ不可避的な順序を持っているにすぎないというような場合とは異り、そこには合理的な連絡があるのである。そしてあたかもすべての存在が調和をもって組み合わされているように、すべて生起する事柄は単なる継続ではなく或る驚くべき親和性を現わしているのである。
(新訳)
後続するものは先行するものに緊密に結びついて継起するのである。なぜなら、それはばらばらに分離したものの一種の枚挙、それも専ら外からがっちり強制された性格の枚挙といったものではなく、十分な根拠づけをもつ連結である。そして存在する諸物が一大調和をなしつつ配置されているごとく、生起するものもまた単なる継承でなく賛嘆すべきある種の近親性を顕示しているのである。
以上引用終わり。ことによると、新訳のほうが原語に忠実なのかもしれない(ギリシャ語を全く解さない自分には、それを検証することができない)が、少なくとも、読み物としては旧訳に軍配をあげざるを得ないと思う。
長いあいだ勘違いしていたことがひとつ。神谷美恵子さんは、英語訳から重訳したものとばかり思っていたのだけど、原典(古典ギリシャ語)から訳されていたのですね。神谷美恵子ファンとして、この勘違いはかなり恥ずかしいのだけど、戦中戦後のあの混乱のなかで、もっといえば、食べていくことや生きていくこと自体が大変だった時代にあって、これは途方もない偉業ではないですか。改めて尊敬する。
ところで、この本に全然関係ないことだけど、本のなかほどに、馬券のコピーがはさんであった。馬の名前が「アタラクシア」というのでこの本にはさんだのかもしれないが、全然記憶がない。「2000年5月28日、第67回日本ダービー」と書かれている。この馬のオーナーは、どういうつもりでこの名前をつけたのだろう。
藤岡陽子『陽だまりのひと』(祥伝社文庫、2019) [本と雑誌]

『ホイッスル』(光文社文庫、2016)に登場する小さな法律事務所が、本作の舞台になっている。法律家の仕事をとりあげた小説はたくさんあるが、「説明」なしでわかる範囲には限界があるし、説明を始めると小説がつまらなくなってしまうし、書くのが難しいジャンルだと思う。でもこの作品は、じゃまにならない程度に理解することができ、楽しむことができる。
波乱万丈・驚天動地の物語とか、ストーリーが入り組んだミステリとかを望む読者にとっては、盛り上がりやオチに欠けるように思えるかもしれないが、むしろこのあっさり感が、何もかも詰め込みすぎの小説にへきえきした後では、すがすがしく感じる。続編希望。
津原泰水『ヒッキーヒッキーシェイク』(ハヤカワ文庫、2019) [本と雑誌]

話がどんどん飛んでいく。省略されている部分が多く、想像で補って読むので、映画を見ているような感じ。ついていくのが大変だが、登場人物の描き方に作者の愛情が感じられて(それぞれの居場所を用意しているところや、必要以上に持ち上げたり落としたりしないところなど。そういう場面では、不意にゆっくりになる)、この人最後はどうなるのだろう?という興味で最後まで読ませる。
おおうちそのよ「歩くはやさで旅したい」(旅行人、2018) [本と雑誌]
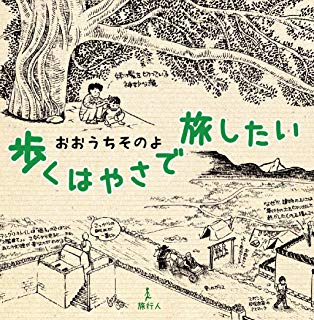
これが「どのような旅の本なのか」と問われると、説明が難しい。
同じ場所に同じカメラを構えれば同じ写真が撮れるとは限らないのと同様、同じ風景を見ても、この作者の目には、このように映るのですね。俳句という文芸は、感じ取る力と言葉に置き換える力の両方が必要なわけだけど、このように感じ取る目を持っていること自体が、稀有な感じ。
本書は、旅の具体的な情報を求めて読む本でもなく、紀行文やエッセイとも違う。しいて言えば、旅とは何か、について、直接論じることなく示唆している本というべきだろうか。蔵前仁一さんの「ホテルアジアの眠れない夜」とか田中真知さんの「孤独な鳥はやさしく歌う」とはまた違った、旅することが人間にもたらす何かを考える上で重要な気づきが得られる名著。「旅行人」連載時に楽しみにしていたコーナーでもあり、腰巻きで蔵前さんが「どうしてもこの本を出したかった」と書いていることに深く共感する。
スコット・ジュレク『NORTH 北へーアパラチアン・トレイルを踏破して見つけた僕の道』(栗木さつき訳、NHK出版、2018) [本と雑誌]
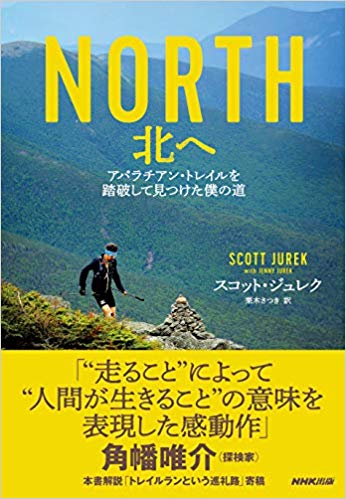
アパラチアン・トレイル(AT)を南から北へ走って、最速(最短時間)踏破記録をめざす話、と要約してしまうと身も蓋もないのだけど。
時間との戦い。自分との戦い。サポートする配偶者の視点と本人の視点が交互に語られることで、ものの受け止め方の違いみたいなものを描き出すことに成功している。
また、ストーリー的にも面白い。気楽にスタートしたものの、すぐにケガをしてしまってそこからのリカバリーに苦労するとか、著名なランナーなのでしだいにファンが増えてきて、楽しかったり鬱陶しかったりするとか、アンチが湧いてくるとか。最後は専門家集団?がサポートチームとなって記録達成に向けて全力で支援する。このあたり、最初から最後まで1人で歩いていたら、周囲との相互作用が描かれないことになるので、こういう物語にはならない。
それらを楽しく読んだ上で、ちょっとはみ出すとすると、ロングトレイルは来る者を拒まないので、最速踏破記録をめざすことも一興だと思う。だからといって(そのような誤解はないと思うが)トレイルは競技のためのトラックだと思われても困る。そのあたりは、むしろ読む側の課題なのかもしれない。同じトレイルを歩いても、以前にこのブログでも紹介した加藤則芳『メインの森をめざして―アパラチアン・トレイル3500キロを歩く』とはだいぶ趣が違う。どちらがいいとか悪いとかではないが。
マーク・ヴァンホーナッカー『グッド・フライト、グッド・ナイト』(岡本由香子訳、ハヤカワ文庫、2018) [本と雑誌]
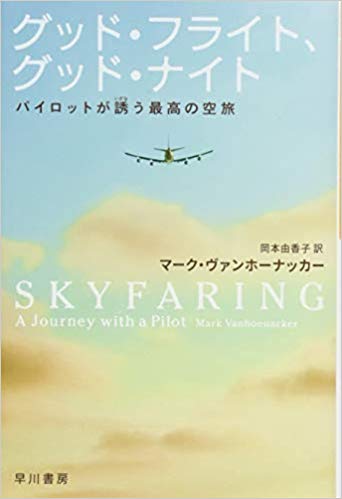
山ほどある「航空関係者が語るエアラインこぼれ話」とか「パイロットが語る飛行機物語」の類とは一線を画し、独自の詩情をたたえた(しかし、下手に文学づいていない)エッセイ集。従って、そのようなこぼれ話や雑記を探す向きには物足りないかもしれない。多少おおげさにいえば、「人間の大地」や「夜間飛行」に通じるような詩情(直截なものではないが、通底するものとしての詩情)が感じられる。他方で、実用書としての価値がないかというとそんなことはなくて、気象や天文についての知識を大幅に増強してくれる一冊でもある。
上記のような詩情を感じられる理由は二つあって、ひとつには、文化の多様性に対する著者のゆるぎない支持や信頼があること、もうひとつには、さまざまな古典を適切に引用しながら、自分の言葉を選んで表現を練り上げているところだと思う。
さまざまに変化する空や水や人の描写は、時として俳句の写生を思わせるところもあり、また、飛行機を飛ばすために働いているさまざまな人々の強い仲間意識がほほえましく感じられる。この本を読んだあとでは、空港や機内、窓から見える地上や空の上の景色も少し違って感じられることだろう。
深緑野分『戦場のコックたち』(東京創元社、2015) [本と雑誌]

文庫になるまで待つとか言ってないで、もっと早く読むべきだった。
一応謎解きの形式になっているのだけど、そういうジャンル分けが無意味に感じられる力作。これが長編デビューとは、にわかには信じられないほど。
2018年の個人的第2位が、最後の最後にやってきた(ちなみに1位は吉田裕『日本軍兵士』(中公新書、2017))。
エピローグを読みはじめて、最初「なんでこんな余計なものを?」と感じたが、そうではなかったのですね。このエピローグこそが、この本のコアなのでしょう。
松家仁之『火山のふもとで』(新潮社、2012)【一部ネタバレ注意】 [本と雑誌]

文庫になるのを待たずに、すぐに読めばよかった本シリーズ第2弾。
ことし最初に読んだこの1冊が、今年のベストワンになるはず。大げさにいえば、小説という形式に、まだこのような可能性が残っていたことがとても嬉しい(しかも、何かすごく新しいことが試みられているわけではないのに)。
一つ一つの場面が、すみずみまでピントが合った風景写真のように、色彩、音、におい、温度などこちらの五感を総動員してくれるのに、それがちっともうるさく感じられないことに感心する。よくよく慎重に考えて正確に選び抜かれたことばで綴られた物語だからなのだろう。
また、結末のつけ方に感服する。この物語はどのように終わるのだろうと心配させておいて、こういう着地をしてくれるのですね。終わってしまうのがもったいなくて、最後の2章ぐらいを1週間かけてなめるように?読んだ。
個別に立ち入って感想を述べると、麻里子の造形と雪子の造形が周到であること。ひとことで言い表している部分もあって、たとえば
(以下引用)
麻里子の笑顔は、向けられる先が誰なのかいつでもはっきりとしている。ところが雪子の笑顔はただそこににじみ出て、誰が受けとろうが受けとるまいがかまわないといった風情に見える。それは雪子の不思議なおだやかさがどこからやってくるのかわからないのと似ていた。(p.147)
(以上引用終わり)
のようなところは、それ以外の表現に置き換えるのが難しいほどの説得性がある。その雪子が最後の1ページで(p.377)徹に向けるひとことは、これはもう参りましたとしか言いようがない。引用するのがもったいないので、ぜひ本屋さんでこの本を買って読んでほしい。
また細部に立ち入ると、例えば、徹と麻里子の大事な場面(pp.78-9)で棚から取り出すLPがブラームスのピアノ協奏曲第2番で、しかも徹はB面をかけるのですね。つまり、意図して第3楽章から聴いているわけです。できすぎというか…しびれる。もっともこの場面に限らず、ここに出てくる人たち全員の文化資本の蓄積ぶりってすごすぎませんか、と(感心しつつも)僻みたくなることも事実。
さらに、長い時間の経過とともに、徹のものの考え方が変化していくことも見逃せない要素で、かつてあれほど違和感を感じていた船山圭一の設計が、「当初の計画どおり、あるいはそれ以上の広がりをもって着実に機能してい」ることを肯ったり、「初めての夏に、毎日のように聴いた声。しかし、どうしてもその鳥の名前が出てこな」かったりする。こういうところも、この小説の説得性に寄与しているのだと思う。
北村薫『中野のお父さん』(文春文庫、2018) [本と雑誌]
面白くてスイスイ読めるし、なるほどと思わせるところも多いのだけど、息詰まるような展開とか、読後に残る余韻や重い感じとかがもう少しあってもいいような…


北村薫『八月の六日間』(角川文庫、2016) [本と雑誌]

ふだんアマゾンの読者レビューを読まないのだけど、何かのはずみで本書のレビューを見たら、主として高齢の登山者と思われるレビュワーから「実際の○○山はこうではない」とか「山と関係ないことが書かれていて余計」とか書き込まれていて、笑ってしまう。山のガイドブックではないのだから、お門違いとしかいいようがない。だいいち、それを言い出したら、主人公は忙しくてたまにしか山に行けない割にはずいぶん健脚なんですね、などと無限に突っ込むはめになってしまって、全然面白くない。
こういうお門違いが生じる理由は、山を舞台にするとどうしても実在の山や山小屋を持ち出さざるを得ないからで(まったく架空の山でも小説は書けそうだが、あまり面白くなさそう)、これが例えば野球やサッカーを題材にした小説だったら、ボールが消えようが、弱小チームが甲子園に出ようが、要するにどれほど現実離れしていても「設定が安易すぎる」とか言う人は少ないと思うのだけど、「槍ヶ岳」とか「大天荘」とか固有名詞が出てくるので、ぐだぐだ言いたくなってしまうのも無理ない面もある。
また、昨今のご時勢では、ここに書いてあること(だけ)を全部そのまま真に受けて、暗くなってから山小屋に着いて平気とか、ザックの中はお菓子ばっかりとか、本当にそういう登山者が現れないとも限らないので、本文と解説(瀧井朝世さん)のあとにわざわざ、
(以下引用)
---------------
「この作品はフィクションであり、(中略)作品中で描かれている登山時間や必要な道具類などはあくまで「主人公の場合であり」、季節や天候、コース状況、各人の体調や経験などによって大きく異なります実際の登山の際は、山小屋や登山用品店のスタッフなどプロの助言のもと、万全の装備で無計画な登山は避け、無理をせず自分のペースを守って登るようにしてください。(以下略)(p.323)
---------------
(以上引用終わり)
と書かれている。だから本当に、山のガイドブックではないんだってば。それにしても、地図も登山ガイドも読まず、この本に依拠して山行計画を立てる人がいるのだろうか…豆腐の角に(以下自粛)
この数年でたまたま、山を舞台にした小説として『春を背負って』『山女日記』そして本書『八月の六日間』を読んだが、それぞれに違った特色をもつ作品で、登山経験があろうとなかろうと、楽しめるのではないか。
藤岡陽子『手のひらの音符』(新潮文庫、2018) [本と雑誌]
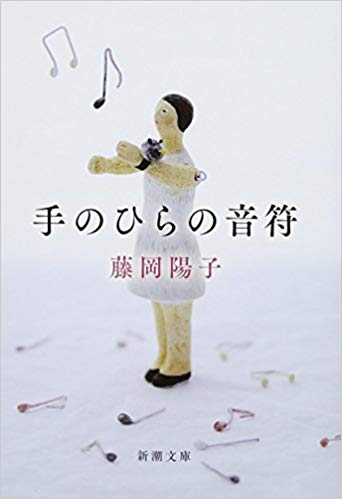
以前に友人から勧められてから、気になりつつ手にとる機会がなかった本が地元の書店の文庫平台に積まれている。腰巻きの惹句に「良い小説」とあるのはちょっと引っかかるところで、小説に「良い」「悪い」のモノサシを持ち出すのは違うと思うが、そう表現したくなる気持ちは、読んでみてよくわかった。
この小説には明確に「いい人」とか明確に「悪い人」というような人物は登場しない。それぞれが弱いところを持ちながら、なんとか道を模索していく過程で、助け合ったり傷つけあったりする、そういうストーリーが、読者の共感を得ているのだと思う。
また、俳人(のはしくれ)としては、季節の描写がよくできていて、それがストーリーに立体感をもたらしているところも見逃せない。例えば、
(以下引用)
窓の向こう側の新緑を、水樹は眺める。目に染みるような田んぼの緑が息をのむくらいに美しい。新幹線は滋賀を通過したところだ。東京を出てからまだ二時間も経っていないのに、光を帯びた瑞々しい田や畑が
果てしなく続いていて、それをぼんやり眺めているだけで固く張っていた心が緩んでいく。(p.64)
(以上引用終わり)
というようなところ。
あとがきを読んでみて、この作家には既に何冊も著作があることがわかったので、さっそくもう1作品、『いつまでも白い羽根』を読んでみることにする。
中脇初枝『世界の果てのこどもたち』(講談社文庫、2018) [本と雑誌]
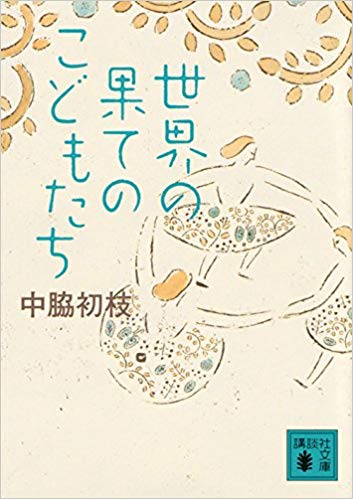
腰巻きに「2016年本屋大賞受賞」と書いてあって、よくよく見たら本屋大賞「第3位」と書いてある。これほどすばらしい本が第3位なら、第1位や第2位はどんな本なのかと疑問に思い、調べてみたが…
あの本とあの本ですか。偶然だがどちらも読んだことがある。どちらも面白かったけど、私なら段違いにこっちだと思うのだが。
内容について多言を要しない。属性でものを言うことの不毛さ。どのような属性の下にも、しょうもない個体とすばらしい個体が混在しているという現実。仮に属性間に何らかの差があったとしても、その差より個体差のほうがずっと大きいということ。
ひとつひとつのエピソードがリアルなのは、詳細かつ大量の取材があって、そのほんの一部分を使っているからだと思われ、タイムリミット的なことも考えると、その点でも価値ある一冊。『アグルーカの行方』と続けざまに、まだ7月だが今年のベスト1が2冊到来。
角幡唯介『アグルーカの行方』(集英社文庫,2014) [本と雑誌]
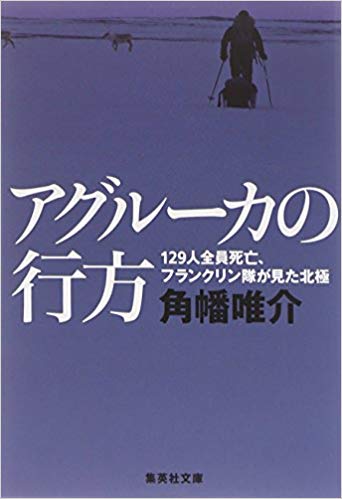
もっと早く読めばよかったと悔やまれる一冊。
旅や冒険の記録を面白く書くことは、とても難しい。書き手にはわかっている面白さが、読み手には自明ではないからだが、それをクリアしたものだけが作品として生き残っていくことになる。だから、新しい書き手にはなかなか手を伸ばしにくいのだけど、これは逆に、読むのが遅かったという気にさせられる傑作。
(すでに多くの賞を受賞しているのだから、分かりきっているではないかと言われればそうなのだけれど)
内容について改めて説明するのも余計かもしれないが、北西航路を探索に出て行方不明になった1845年の英フランクリン隊の足跡を実際に追っていくものだが、まずその構成の妙に感心させられる。つまり、史実を追って、現実の冒険(調査)と過去の記録が交互に現れていくのだ。その繰り返しの中で、今なお謎とされているいくつかのことがらについて、著者の考え方が順番に示されていく。むろん著者は結論を得た上で書き始めているのだけど、わかっていても、著者といっしょに推論をしていくような気分を味わうことができ、たいへん楽しい。
また、その調査も、さまざまな障害に阻まれながらも、現場をきちんと踏んでいこうとする姿勢が貫かれており、単に「仕事」として行われる調査とは趣を異にする。ジョアヘブンの村で訪ねたルイ・カムカックのこの言葉(312頁)は、何気なく書かれているが、著者が引き出した名言というか、著者が叫びたいことを相手が代弁してくれているのではないだろうか。
(以下引用)
みんな机の上で資料をひっくり返しているだけさ。こんな遠くまで来る者はほとんどいないんだよ。
(以上引用終わり)
冒険の記録は数多くあり、過去の事跡に関する研究も数多くある。しかし、両者をこのような形で融合することで、この作品は別の価値を得たといえるだろう。
次に、著者は冒険家といわれる人であるからして、実際にさまざまな危険を伴う何かを経験して現在に至っているわけなのだけど、登山にせよ、探検にせよ、そうした危険を伴う行動に人がのめりこんでいく理由について、自分の経験をまじえて説得的に説明していることに感心する。
説明によれば、それは、そのような命の危険が、逆に「生命の実体」とでもいうべきものを照らし出し、人に居場所を与えるからだ、といったことになる。
それまでの探検の過程で散々な目にあったはずのフランクリンが、なぜ高齢にもかかわらず再び危険を求めて探検に出たのか、という点についての以下の説明は、非常にわかりやすくハラに落ちるものだった。
(以下引用)
分かりにくいのは彼が、他人には悪夢にしか聞こえないようなこのような体験にも懲りず、その後ものこのこと北極探検に繰り出したことだろう。おそらく彼は最初の体験で荒野に魅せられてしまったのだろう。不毛地帯のただ中で生死の境を彷徨ったにもかかわらず、ではなくて、生死の境を彷徨ったからこそ彼はまた探検に出かけたのだ。ふらつき、腐肉を漁り、靴を食い、贅肉が削げ落ちたことで、圧倒的な現在という瞬間の連続の中に生きるという稀な体験をすることになった(…)初めて生きるものとしての強固な実体が与えられることになった。(429頁)
北極の氷と荒野には人を魅せるものがある。一度魅せられると人はそこからなかなか逃れられない。それまでふらふらと漂流していた自己の生は、北極の荒野を旅することで、始めてバシッと鋲でも打たれたみたいに、この世における居場所を与えられる。それは他では得ることのできない稀な体験だ。(432頁)
この部分を読んでいてふと思ったのが、ジョン・クラカワーの「荒野へ」(集英社文庫)だ。あの話でクリス・マッカンドレスが人里を離れた荒野にのめりこんでいく理由が、上のように考えるとよく説明できる。
控えめで抑えられた筆致といくぶんの諧謔味も、この本を好ましいものにしている(自分を突き放して笑うことができるのは、1人称で本を書く上では重要なところだと思う)。また、当時のイギリス的なものに対する適度な距離(持ち上げもせず、落としもしない)もいい。限界を示しつつ、否定はしないということは、けっこう難しい。これは、われわれもまた現在の「時代」の枠の中でしか生きていないという認識があるからできることだと思う。
最後に、地図がある程度充実していることは、読んでいく上で便利なだけでなく、地図自体が読書の対象と考える私にとっては、とてもありがたい(本棚から別の地図帳を持ち出してきて参照しなければならないようなノンフィクションは、けっこうある)。
池澤春菜が選ぶ池澤夏樹の10冊(『本の雑誌』417号) [本と雑誌]

池澤春菜さんは以前から『本の雑誌』誌に書評を寄せられていたので、いずれ実現すればいいと思っていた“夢の企画”がついに登場。池澤夏樹ファン、池澤春菜ファン、ついでに福永武彦ファンもただちに書店に走るべし。
まず、池澤夏樹のたくさんの著作(翻訳や編集を含めて)をよく読んでおられることに驚く。ここで10冊全部を紹介するとネタバレになってしまうのでやめておくけれども、ひとつだけ紹介すれば、数ある著作から「最も長い河に関する省察」を選んでくれたことに感謝。あれはバックパッカー必読の一冊だと思う(36年前の本で、現在は入手不能だが、同じ版元の『池澤夏樹詩集成』で読むことができる)し、あの中に入っている「午後の歌」には幼いころの池澤春菜さんが詠まれている。
ちなみに藪柑子が選ぶ池澤夏樹の10冊は、以下のとおり。特に順位はない。
『池澤夏樹詩集成』(書誌山田、1996)
『タマリンドの木』(文藝春秋、1991)
『南鳥島特別航路』(日本交通公社、1991)
『むくどり通信』(朝日新聞社、1994)
『ハワイイ紀行』(新潮社、1996)
『パレオマニア 大英博物館からの13の旅』(集英社、2004)
『異国の客』(集英社、2005)
『風神帖』(みすず書房、2008)
『骨は珊瑚、眼は真珠』(文藝春秋、1998)
『言葉の流星群』(角川書店、2003)
本を読む時間がほしい。
井田良・佐渡島紗織・山野目章夫『法を学ぶ人のための文章作法』(2016、有斐閣) [本と雑誌]

本のタイトルは『法を学ぶ人のための…』だが、むしろそれ以外の人が読むべき内容かと。なぜならば、法を学ぶ人は遅かれ早かれ司法試験で文章力が試されるのに対し、それ以外の大多数のひとびと(藪柑子もその中に含まれる)は、文章作法のトレーニングをする機会もほとんどないまま社会に放り出されるわけで、しょうもないハウトゥー本を読むくらいなら、本書のほうがずっと役に立つのでは。
強く印象に残ったのは、「段落の用い方」という箇所(PartⅢ-4)に出てくる著者のつぶやきである(この章は、山野目先生が書かれている)。
(以下154ページから引用)
本当は,「どこで改行するかをよく考え……自覚的に段落の機能を設定する必要がある」(→PARTⅡ2)。喫煙者自身の健康への影響と,受動喫煙とを段落を改めて論ずることは意味があるにちがいない。否,段落の取り方は,それしかないであろう。イ・ウ・エを改行しないで続け1つの段落とし,その忍耐の後に,今度はオ・カ・キを1つにまとめる,ということすらできない,ひ弱な知性の若者たちに場合によっては司法権力を委ねなければならないとしたら,それは,私たちの文明の大問題ではないか。
(以上引用終わり)
文の終わりで、ここで改行するか?それとも意味上のまとまりを考えて改行せずに続けるか?という選択は、書き手の側では常に発生するのだけど、それを読んで採点する側は、ここまで熱意をもち、またつきつめて考えているのですね。幸か不幸か、藪柑子は若者ではなく、また司法権力を委ねられる心配も皆無なのだけど、そうであっても、こういう惰弱なブログを開設して、明確でも合理的でもない文章を、段落の設定も考えずに適当につづっていると、やがて地獄送りになりそうである。反省。
もう一つ、これは内容自体の適否というよりその例えの重さに遠い目になってしまうのが、イントロダクション(この部分は、井田先生が書かれている)で、こんな表現がある。
(以下3ページから引用)
よく知られた喩えをここで借用すれば、皆さんはすでに大海原をそれぞれの船で航海中なのです。いま致命的ともなりかねない船の不具合を発見したのですが、これから港のドックに戻って修理している時間はありません。それに、出発した港がどこにあるか、もう遠くてわからないのです。むしろ目標を目指して公開を続けながら、海上にて皆さんの大事な船を修理していこうではありませんか。本書はまさにそのために役立ってもらいたいと思っています。
(以上引用終わり)
一段落まるまる引用してしまったのだけど、なかほどの「それに、出発した港がどこにあるか、もう遠くてわからないのです。」という一文に、じわじわと来るものがあるのですね。おっしゃるとおり、もう遠くてわからない上に、わかったとしても引き返せないのですよ。自分がトシだからそう思うのかもしれないのだけど。
ともかく一読をおすすめしたい一冊。
川北稔『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書、1996) [本と雑誌]
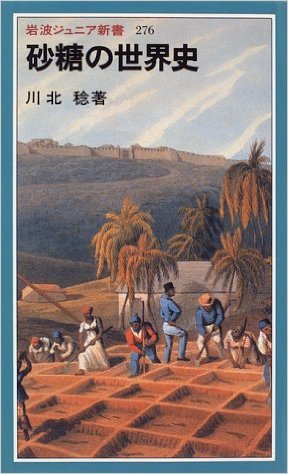
ウォーラーステインの「世界システム論」の読者なら、とりたてて大きな発見があるわけではないのだけど、私たちの生活に深くかかわる砂糖が、どのように世界商品に成長していったかという過程がとても面白い。それは同時に、近代のイギリスの経済史そのものということもできる。
指摘されている現象自体には同意だが、理由について疑問な点がひとつ。
同様の世界商品に成長したタバコのプランテーションと砂糖のプランテーションを比較して、タバコ農場主は現地に定住して現地の社会資本を幾分なりとも整備した(だから本土では社会資本が発達した)のに対して、砂糖農場主はイギリスに住まっていて、現地には全く無関心だった(だからカリブ海諸国では社会資本が発達しなかった)という説明になっていて、その理由を気候の差に求めているのだけれど、それだけなのかという疑問は残る。ここのところ、ちょっと話が単純すぎないか。
藤本朝巳『松居直と絵本づくり』(教文館、2017) [本と雑誌]

福音館書店といえば松居直、松居直といえば福音館というぐらい有名な編集者で、石井桃子さんや瀬田貞二さんたちとともに日本の児童文学の一角を切り開いたパイオニアでもあるこの人の仕事を、若い児童文学研究者がたどっていく本。松居氏へのインタビューも収録されていて、それが本文の内容と一部かぶっているのはちょっと残念だけど、この記録自体は貴重で、後世に残されるべきものと思う。
いちばん衝撃的なエピソードは、創刊直後の「こどものとも」で、ある有名な文学作品をとりあげる(絵本にする)ことを決めた松居氏が画家に頼みにいく場面だ。売れっ子であったその画家は、しかし病に臥せっていて、松居氏が練馬区の都営住宅を訪ねてご夫人に用向きを伝えると、「○○(その画家の名前)は伏せっておりますので、絵が描ける状態ではございません。」と言われてしまう。しかたなく引き下がろうとすると、奥から「その仕事やる、待ってもらえ」と声がかかり、画家は布団の上に上半身を起こして、「××××(その文学作品の作者)、やりますよ。その仕事やれるなら死んでもいい」と松居氏に言ったという。
(pp.46-47)
この話が衝撃的である本当の理由は、この作品が絵本として実現した直後、この画家がほんとうに亡くなってしまったことにある。本書では「いわば、○○さんの最期の作品です。病を押して描き上げたのには、よくよくの思いがあったからに違いありません。」と控えめに書かれているが、ちょっと戦慄を覚えるような話である。
付言すると、絵本化されたその作品自体が、xxxxが死の床で最後まで手を入れていた作品(かつ、私の好きな作品)なので、何かの因縁ばなしのようで、二重にゾクッとしてしまうところである。
さらにさらに、ある画家がこの絵本を読んで絵本をつくろうと決意し、松居直を訪ねてきて「こどものとも」からデビューする話(pp.140-142)とか、後年自らも絵筆をとって、同じ文学作品を別の出版社から絵本化したというエピソード(pp.48-49)が紹介されていて、よくよく因縁めいた作品でもあると感じる。
こうしたエピソードを措くとしても、巻末に掲げられている「松居直編集による月間絵本『子どものとも』一覧(1~149号)」を眺めると、きら星のようなというのか、今でもよく知られている作品がずらりと並んでいて、すごさを感じる。
若菜晃子『街と山のあいだ』(アノニマ・スタジオ、2017) [本と雑誌]

山の本というより、山を題材にした人間模様ともいうべきエッセイ集だが、静かな中に滋味があって好ましい。
登山経験のない大学生が山と渓谷社に入社して、まあ山と渓谷社であるからして当然のように山岳雑誌の編集部に配属されて、ドタバタしながら編集者として成長していくのだけど、その過程で出てくる先輩編集者や同僚、執筆者がいずれも、俗なことばでいえば「キャラが立っている」というのか、ユニークな人々。これらと並行して、親や家族、地元の人々、他の登山客など、山をめぐっていろいろな人々が現れる。
そうした人々との関係のひとつひとつを、あたかも詩のように(という表現が当たっていなければ、木炭で描かれたデッサンのように)しみじみと描いていく話なのだ、と書いてみると、なんだかちっとも良さが伝わらないのが残念。味付け濃厚な山岳本に飽きたらぜひこの本を。

