中井久夫集4 「統合失調症の陥穽 1991-1994」(みすず書房、2017) [本と雑誌]
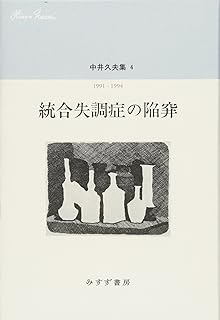
目立たない論考だが、「危機と事故の管理」を読むと、管理者としての中井久夫さんの素顔が現れていて、精神科医による文章が世の中にたくさんある中で中井久夫さんがよく読まれる理由の一つに、管理者としてのセンスの良さ(をうんぬんする立場にないけれども)があるのだと思う。人命を相手にする仕事だけに、現場で起こるアクシデントにもシリアスなものが多いわけだが、それらに対する臨み方について語られていることは、医療以外の世界で管理者を務めている人々にとって、たいへん納得のいくものであり、また示唆に富むものではないかと思われる。
もう一つ、私が中井久夫さんの論考に共感を覚えるのは、「症例検討会では、住んでいる地域の地理的条件を私はよく問題にする。」(『治療文化論再考』p.285)姿勢だ。「入れ物の形に中身を合わせるように体験を加工しがち」(p.284)な者が多い中、自分はそうではないと明言しているので、この点については自信をお持ちだったのだと思う。この基準ないし座標の持ち方が、中井さんの著作に影響を与えていることは相違なく、それが読者を増やしているのではないかと想像する。
中井久夫集3 「世界における索引と徴候 1987-1991」(みすず書房、2017) [本と雑誌]

はたと膝をうつ、という言葉があるのだけど、統合失調症の典型的な症状でる妄想について中井久夫氏が書いているこの一節は、なかなかうならせるものがある。
-------------
自然な“虫の知らせ”(予感や余韻)に耳を傾けないからこそとんでもない妄想に頼るのである。妄想が何であれ、妄想者は信じてもほぼ安全であることを疑い、信じる根拠のないものに軽々しくとびつく。容易に信じない懐疑者であると同時に軽信者でもある。彼らを軽信させる大きな動因に権力意志がある。私は俗的な権力意志ぬきの妄想者を知らないくらいである。
--------------
以上引用終わり(「統合失調症の精神療法」p.101)
もしこの指摘が事実だとして、さらに、妄想者が総人口に対してそこそこの比率で存在するとしたら、これによって説明のつく社会現象がありそう。あれとかあれとか。
中井久夫集2「家族の表象 1983-1987」(みすず書房、2017) [本と雑誌]

「治療文化と精神科医」で描かれる日本の地域性(地方ごとの疾患の現れかた)が、自分の実感と(また、世間でよく言われることと)一致しているのに驚く。単なるイメージでなく、実際の疾患の内容自体に大きな地域差があるとすれば、それは精神的風土に関して、少なくともこの稿が書かれた時点において、国内に大きな地域差が実在したことの裏付けに外ならない。
めっぽう面白いのは「ジンクスとサイクルと世に棲む仕方と」で、しかしいい加減な話ではなく、それが存外合理的なものであることを指摘し、また、医療の世界自体がそうした巨大な自然現象に対して小さな力しか持ちえないことを述べる。「医療の世界が、船乗りの世界のような、ジンクスの多い社会に思えてくる。いかに大きな船舶でも大洋に比べてはものの数ではない。」(p.68)「あかあかと灯をともしながらひっそりと静まりかえっている深夜の病院も、暗夜の海を行く巨船である」(p.69)というくだりは、なるほどそうだと思わせるものがある。(「ジンクスとサイクルと世に棲む仕方と」)
もう一つ、「強い相互作用と弱い相互作用」という考え方は、家族だけでなく、社会のあらゆる場面で有効なツールになりうるもので、例えば直属の上司と部下の関係が強い相互作用だとすれば、同期入社の社員同士はやや強い相互作用、社内の勉強会やサークルは弱い相互作用ということになるのだろうけど、いまどきの組織で求められているのは、弱い相互作用にもとづいた「社員の安全な居場所」をつくることだったりする。(「『つながり』の精神病理」)
中井久夫集1「働く患者 1964-1983」(みすず書房、2017) [本と雑誌]
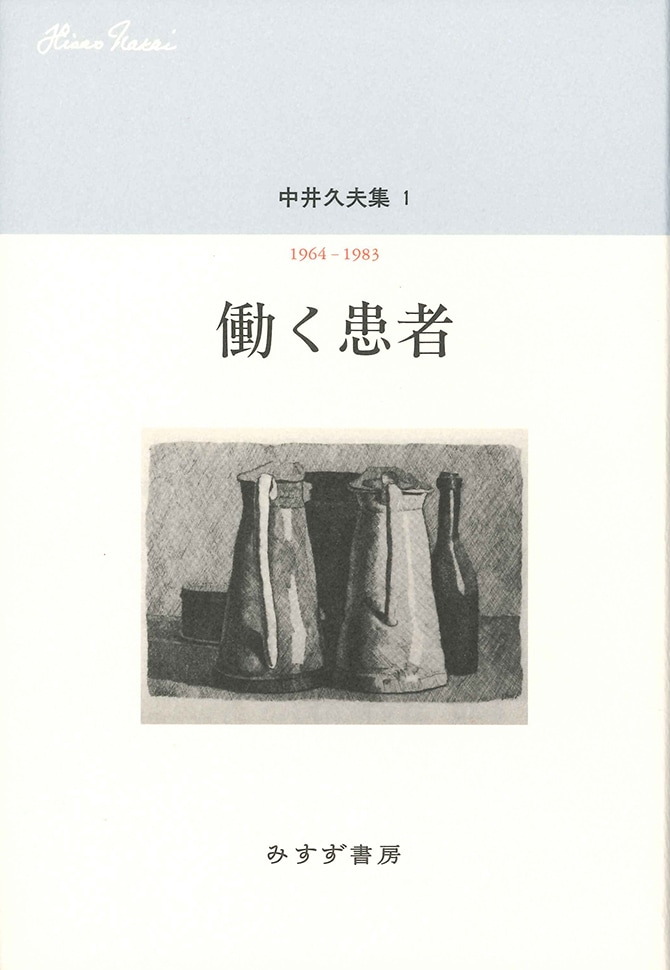
ああそうだったのか、と思う。
初めて中井久夫さんの著作に接したのは、阪神大震災後の一連の著作だと思っていたのだけど、この巻の最後に納められている「精神科医としての神谷美恵子さんについて」の初出は、同じみすず書房から出ていた「神谷美恵子著作集別巻 人と仕事」(1983.4)なのですね。そうすると、これがおそらく、二十歳そこそこの自分が初めて読んだ中井さんの文章になるのだと思う。
その最後の章である「8」に記されているエピソードは、神谷美恵子さんの存在の大きさを描くとともに、中井さんの眼差しをも感じさせる名文だと思う。また、最初に接したのが精神科医としてのもっとコアな内容だったら十分に理解することができないまま終わったであろうことが明らかなので、この出会いは幸運だった。
津村記久子『やりたいことは二度寝だけ』(講談社文庫、2017) [本と雑誌]

それぞれの記事の初出が知りたい。特に、「『女が働くということ』に関する原稿」(pp.230-232)の初出が。この記事は、最後のエピソードがすばらしい。今の津村さんなら、また別の表現を考えるかもしれないが。
エッセイを読むことでその作者の小説がよく理解できることはままあるが、この本もそうで、津村さんは、規範を示してそれに合わないものを排除するというスタイルをとらない。むしろ反規範といってもいい。しかし何でもありなのかというとそうではない。内面化された「構え」のようなものがある。それを掘り下げているのは本書ではなく、深澤真紀さんとの共著「ダメをみがく "女子”の呪いを解く方法」(集英社文庫、2017)で、「どうしてもあかんこと以外はやり合ってもしょうがないのだから、やりすごすとか気にしないとか時期をずらすとかしかない」という津村さんの達観が淡々と語られる。ここでは失礼ながら、深澤さんが津村さんに人生相談をしている風になっていて、知識や規範にがんじがらめに縛られ、かつ自分語りをやめられない深澤さんに対して、津村さんがあっさりと薄味の答えをするのだけど、どう考えても津村さんの方が10歳ぐらい年上に感じられる。言葉の成熟度や選ばれ方のレベルが違うということなのだろう。
全然本題と関係ないのだけど、芥川賞受賞作「ポトスライムの舟」の原稿データを編集者あてにメールで送信したあとのことについての記述(p.207)は、津村さんがどれほど考え抜いて表現を選び、小説を仕上げているかがうかがわれて面白い。
藤岡陽子「金の角持つ子どもたち」(集英社文庫、2021) [本と雑誌]

中学受験って自分の全くあずかり知らぬ世界なのだけど、受験を通じてこどもが大人を成長させていく物語も成立しうるのですね。この点に感心することしきり。
藪柑子的には、多くの方が言及しておられる加地の兄弟愛よりも、受験前日の加地と宝山美乃里の会話、というより加地の美乃里への言葉が印象に残った。ここで二人は先生と生徒という役割を離れて、まったく対等に話している。バトンを渡す加地のさしせまった心情(=そこまで読みすすめてきた読者の思いでもある)も、それを受け取る美乃里の気迫(=そうでない者がごまんといるだけに)も、どちらもすばらしく、涙なしには読めない。全藤岡作品中(って、全作品読んでいるわけではないのだけど)屈指の名場面だろう。この場面だけでも、読んでよかったと思える。
また、ありふれた感想になるが、人に何かを教えることの難しさや、逆に人から何かを学ぶことの面白さが、この本には山盛りになっていて、教えるにしても教わるにしても、この点をいつも心の隅に置いておきたいものだと思う。
津村記久子『サキの忘れ物』(新潮社、2020) [本と雑誌]
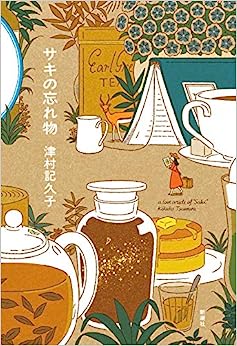
第1話「サキの忘れ物」がしみじみといい話。特に、終わり方がすばらしい。
また、最終話「隣のビル」は、登場人物が理不尽な職場に疲れ果てていることと、ちょっとファンタジー風味が入っていて、「この世にたやすい仕事はない」を連想させる。
関係ないけど、津村作品には紅茶にくわしい人物が時折登場し(『とにかく家に帰ります』とか)、どれも悪くない書かれ方をするのだけど、何か特別な意味があるのだろうか。
(8.28追記)津村さんの『やりたいことは二度寝だけ』(講談社文庫、2017)を読んでいたら、津村さん自身が紅茶好きで、日常的にたくさん紅茶を飲まれていることが判明。だから描写がすごく具体的になるのですね。
奥山淳志『庭とエスキース』(みすず書房、2019) [本と雑誌]

俳人にはたいていのものが俳句的に見えるから、本を読んだそばから「俳句的だ」と書いても意味がないのかもしれないが、ここに書かれていることは、全部が俳句のように思える。著者にも弁造さんにもそんな意図はまったくないのだろうが、読んでいる方にとっては「眼前のものみな俳句」である。北国の厳しい冬の暮らしと、極度に内省的な二人のやりとりが、それを強く感じさせるのかもしれないが。
目黒考二さんを悼む(『本の雑誌』2023年5月号) [本と雑誌]

1月に亡くなった目黒考二さんの追悼号。自分にとっては目黒さんあっての「本の雑誌」だったので、これからどうなるのか心配だが、ともかく読書という営みを通じて数多くの人とつながっていた方だけあって、弔詞を寄稿されている数々の名前も、さながら目黒山脈とでもいうべき壮観になっている。
しかしそれらのどれよりも、本の雑誌者でいっしょに働いていた(かつては会社の一室に住んでいたわけだから、文字通りいっしょに働いていたわけだけど)人びとのことばが最も印象に残る。いずれも個人的な場所からの、個人的なことばであって、定型文でなくざらざらしているので、それが訴える力になっている(定型文がいけないというのではない。定型文は身を守る盾として有効。ただそれ以上のものが定型文から得られるわけではないというだけ)。たとえば杉江由次さんが書かれた「本の雑誌社『その日』までの記録」の一節(31頁)。
(以下引用)
----------------------------
本屋さんに行くたびに、もうここにある本を目黒さんは読めないのか、そもそも目黒さんはもう本屋さんに行けないのかと苦しくなる。生まれて初めて本屋さんに行くのがつらい。
----------------------------
(以上引用終わり)
これ以上切実な哀悼の言葉があるだろうか。
また、つけ足すとすれば、1つ前の4月号に鏡明さんが書かれていた思い出で、その淡々とした筆致もさることながら、これも鏡さんのふだんの言葉で綴られている分、そうだなあと思わせるものがあった。
(4.25追記)
宇野重規さんがtwitterで、この5月号について書かれている。全文引用してしまうと引用の要件を満たさないことになってしまうが、書かれていることがすばらしいので、おとがめは覚悟であえて引用すると、
(以下引用開始)
-------------------
ようやく『本の雑誌』を入手。この雑誌を創刊した目黒考二さんの追悼号。本を読むことだけが生きがいの変な(変でもないけど)青年が、そういう若者を育てる立場になる。大江健三郎、坂本龍一の死もショックだけど、この人が亡くなったのも、喪失感があるなあ。
--------------------
(以上引用終わり)
宇野さんほど多くの本を書かれ、多くの人を教えてこられた方でも、こういうふうに思われるのですね。そうであれば、私が同じように思うのはちっともおかしくないことになる。
(5.16追記)
それにしても、表紙の「酒と家庭は読書の敵だ!」という煽り文句が笑えるというか笑えないというか、ご本人の口癖だったそうだけど。
自分に読書の楽しみを教えてくれたひとびとの多くは、もう亡くなってしまったか、少なくとも本について話すことはできなくなってしまった。で、自分はそのバトンを次の世代に渡すことができているのかと少し自問する。
(7.10追記)
「旅行人編集長のーと」に蔵前仁一さんがこの号について書かれている。蔵前さんほどの書き手でも、目黒考二(北上次郎)に褒められたことで「僕も目黒さんや椎名さんに褒めてもらったおかげで、物書きとしてやっていけるかもしれないと自信がついた。」と思っているのですね。ちょっと意外。
児玉聡「オックスフォード哲学者奇行」(明石書店、2022) [本と雑誌]
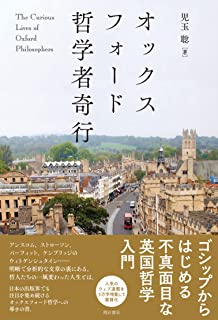
何の面識もない過去の哲学者たちの風変りな言動に、どうしてこんなにワクワクするのだろう。単にワクワクするのみならず、もしこうした哲学者たちのチュートリアルを受けたとしたら、おそらく3秒で粉砕されるだろうけど、自分の学生生活はもっと違ったものになったのではないか(いや、古文書室で過ごした2年間も自分にとっては限界までやり切ったとは思うし、もっと何かできたはずなどと考えるのは不遜なのだが)と考えると、ワクワクを超えてゾクゾクするものがある。
ちょっと目を惹かれたのは、その黄金時代?に、日本からの留学生が1人いたという事実。それも、アンスコムにチュートリアルを受けていたというのだから只事ではない。この方は、帰国後にどうされているのだろうか…と調べてみたら、ライプニッツ研究の第一人者として、慶応義塾でも教えておられたのですね。
あとがきのそのまた最後に、先日読んだばかりの「マルクス・アウレリウス」の著者南川高志先生の名前が出てきてびっくり。考えてみれば京大文学部つながりなので当然なのだけど。
ところで、奇行種って何?
南川高志「マルクス・アウレリウス 『自省録』のローマ帝国」(岩波新書、2022) [本と雑誌]

「自省録」ファンにはいろいろなタイプがあるのだろうけど、歴史好きから「自省録」にアプローチしてきたファンは、当然にローマ時代についての知識の上で「自省録」するのだと思う。だが、そうした前提を欠いた、つまり歴史の知識も哲学の知識も欠いた、自分のような唐突な「自省録」ファンは、エピクテートスやセネカとの共通点や相違点を意識することはあっても、この思想が編まれたローマ時代がどのような時代であったかをあまり意識することがない。そこを埋めてくれたのが本書。
プロローグでこれまでのマルクス・アウレリウス研究について紹介する中で、ご存じ神谷美恵子訳『自省録』に言及されていて、
(以下引用)
「神谷訳は、ギリシア哲学を専門としない方の作品であるが、日本で初めてのギリシア語原典からの訳である。今日ではそのギリシア語の解釈や哲学用語の取り扱いに意見があるのを私は承知しているが、『自省録』の神谷訳を読んだことがローマ帝国史研究を始めるきっかけとなったので、本書でも神谷訳に拠りながら語りたい。(p.7)
(以上引用終わり)
とある。ここにも1人、神谷訳「自省録」で人生が変わった人がいるわけですね(って、変わったどころかそれを職業にされているのだから、自分とは比較にならないけど)。
川端康雄『増補 オーウェルのマザー・グース』(岩波現代文庫、2021) [本と雑誌]

何度も読んだつもりでいたオーウェルの小説、たとえば『1984』を、専門家はこういう切り口で読むのですね。たしかにこういう場面はあったけど、それ以上何も考えなかった自分が、ストーリーを追っているだけだったことを痛感。
あとは、オーウェルが生涯にわたって追求したdecencyと、イギリスのさまざまな文物への執着がどういう関係にあるのか、すっきりと説明してくれたことに感謝。これで落ち着いてオーウェルの著作が読めるような気がする。なお、この章で紹介されている「一九七〇年代にジュラ島を訪れたオーウェル研究家が、現地で知り合った電気工事人から聞いたオーウェルの思い出」が非常に印象的で、この部分(孫引きになってしまうので紹介しないが、441頁)だけでもこの本を読む価値があると思う。この時代にはまだ、オーウェルとやりとりをしたことのある人物が存命だったのですね。そうであれば、調査や探求もやりがいがあったことだろう。
津村記久子『エヴリシング・フロウズ』(文春文庫、2017) [本と雑誌]

読み始めてまもなく、あれっと思う。これって『ウエストウイング』の続編なのでは?
カバーにも解説にもそれらしい記述は一切ないのだが、名前だけでなく、同じ学習塾出身の3人という設定なので、間違いないだろう。もちろん、この本だけ読んでも楽しめるのだけど、『ウエストウイング』でヒロシがかかえていた母親との葛藤が、ここでは別の形で展開される。
いわゆる「見せ場」のようなものがあるとすれば、終盤に二人が駅で別れを惜しむ場面(pp.380-2)だと思うし、事実このシーンは、陳腐な表現だが映画のワンシーンのように美しい。でも、読者がこのシーンにぐっとくるのは、それより手前、二人の気持が通じ合うことになるこの会話(pp.351-2)があるからこそだと思う。そしてここでは、問いかけるヒロシの言葉も、ヒロシの立場でなければ発せない言葉だし、答える紗和の言葉も、なぜ紗和がそのように生きているのか、なぜ紗和の母親はあんなふうなのかまで簡潔に言いつくしていて、そこにいつもの韜晦はない。
そして、これは多くの方が言及されていることだが、そうしたやりとりが、一貫した信念や主義主張にもとづいてではなく、その場で考えてそうしているところが、この本の最大の眼目なのだと思う。理路整然として首尾一貫しているけど内容は(首尾一貫して)どうしようもない大人とかいっぱいいるわけなので、相互に矛盾していてもかまわずその場の最適解を必死で考える中学生の姿に心打たれる。こういうところが、自分が津村作品に惹かれる大きな理由なのだと思う。ついでに言えば、自分が中学生のころは(いや今でもか)、こんな気の利いた発言も行動も全然できなかったわけで、6人ともすごいなと思う。
高橋秀実『はい、泳げません』(新潮文庫、2007) [本と雑誌]

仙台の町を歩いていたら、アーケードに面した本屋の様子に見覚えがある。見覚えがあるのみならず、学生のころ、この本屋に入って本を買ったことがあるような気がする。仙台にはこれまで両手の指ぐらいの回数しか行ったことがなく、そのときもなぜ仙台の町を歩いていたのか思い出せないのだけど、この本屋でハードカバーの本を買って、春先のみぞれ降る中を仙台駅まで歩いたような、奇妙に具体的な記憶が残っている。
記憶の混線がもたらす既視感(←よくある)なのかもしれないが、大昔のことゆえその場で真偽を確かめようがないし、自分の記憶があてにならないこともよくわかっているので、文庫本を一冊買い、カバーをかけてもらい、帰宅してから古い記録と照らし合わせることにした。ーーー
この本、東京行きの新幹線に乗っているあいだに読めてしまうページ数なのだけど、「たいていの人が体を動かしながら、よくわからないままになんとなくそんなものかと考えて済ませてしまうこと」を、どこまでも言語化しようとする凄まじい努力が逆に笑いを誘うというか、おかしくてたまらない。どこまでが計算してズラしているのか、またはどこからナチュラルにズレているのかよくわからないぐらい変てこりんな記述なのだけど。いまだに泳ぎの苦手な自分が強く同意したのは「溺れかけたときの記憶が細部まで鮮明である」という箇所。あれはどういう理屈なのだろう。
文庫版のためのあとがきを読んでさらに驚いたのは、これがどこかの自治体の市民プールみたいな場所で、著者が何者であるか知られずに行われた講習ではなく、青山の高級スポーツクラブ(高級かどうか調べてないけど、場所柄そうなんだろう)で実際に行われたレッスンに基づく作品だったという点。いやむろん、そのことはこの作品の価値を損なうものではないのだけど、生徒が誰だかわかっていてレッスンするとなったら、コーチとしても言葉を選ばざるを得ないというか、自分のレッスンがどう記述されるか意識するわけだから、言語化のための特別な取り計らいが生まれやすいのでは。
さて冒頭の既視感問題に戻り、帰宅して古いノートを引っ張りだしてみる。ノートには1979年1月1日以降、新たに買い求めた本のタイトル・著者・購入した書店の名前・日付・金額が書かれている(2000年1月以降はExcelで作成しているので、ノートの最後は1999年12月になっている)。それによると、
1982年(昭和57年)
50 こころの旅 付 本との出会い 神谷美恵子 みすず書房 7.27 仙台・金港堂
となっている。「50」はその年50番目に買い求めたことを示す。
既視感は幻覚ではなかったのですね。ただし記憶と実際が違うところが2つ。1つは、春先でなく夏だったこと。もう1つは、記憶の中のこの本屋は東を向いて(つまり、南北のアーケードの西側に)建っていたが、実際は西を向いて(アーケードの東側に)建っていたことだ。みぞれの中を歩いたのは、おそらく、次に仙台を訪ねた1984年3月だろう。
いろいろなことが急に思い出されてきた。当時、みすず書房から数か月ごとに出ていた「神谷美恵子全集」を楽しみにしていたのだった。今なら、重い本は地元の本屋で買うのだろうけど、わざわざ旅先で買って読んでいるので、旅行中ずっと持って歩いたのだろうか。
ついでにいえば、神谷美恵子の存在を教えてくれたのは、そのさらに3年前、世界史の教育実習生としておいでになった文学部の学生さんだった。なんで世界史で神谷美恵子なのかというと、「自省録」の翻訳者として教えてくださったのだけど、先生ご本人がお元気だったとして、そんな授業をなさったことは覚えておられるだろうか。
しかし一番肝心なことが思い出せない。1982年7月27日に、自分がなぜ仙台の町を歩いていたのか。本屋に入るぐらいだから一人で歩いていたのだろうが、何をしに行ったのだろう。
それはそうと、この「こころの旅」、実家に置いてきたのだろうか?ひょっとして、今も持っているのではないだろうか?と本棚を探してみると、あった。左は今年のカバー、右が1982年のカバー。


三浦しをん『ののはな通信』(角川文庫、2021) [本と雑誌]

今年のしおや100キロウォークに出走するため矢板駅前の宿に泊まったら、隣に小さな本屋があるのを発見した。当節どんどん本屋が減るなかで、地方の駅前に本屋があることが嬉しく、閉店間際だったので、困ったときの定番である三浦しをんを購入。でも本番前日にうっかり読まなくてよかった。読むのがやめられなくなって徹夜してしまい、寝不足で出走できなくなったに違いない。
しょうもない前置きはともかく、すごい本だった。ほんわかしたタイトルに幻惑されてはいけない。
ネタバレにならないように感想を述べるのは難しいが、ここで問われていることのひとつは、「10代の一時期に経験したことを至上至高のものとして、その後の人生を、いわば余生として過ごすことは可能なのか」ということではないだろうか。
人によって答えが違うだろうが、この本に衝撃を受けた理由は、自分の答えが「YesでもありNoでもある」からだ。単にYesな人や、単にNoな人は、そこまでの衝撃を受けないだろう。少しややこしくなるが、以下に説明する。
中年になってから小中学校のクラス会なんかへ行って、かつての同級生が、人相風体は変わり果てているのに、行動原理やものの見方考え方は驚くほど昔と同じであることを発見した人は多いはずだ。それを「三つ子の魂百まで」とか言うけど、ここから導かれる結論は、「人の性格や、ものの見方考え方の中心部分は、ずっと変わらない」になる。これを上記の問いに当てはめると、Yesつまり「『自分』のコアはずっと続いているのだから、そのように考え続けて生きていくことは可能である」ということになる。
他方、こどもと接していると、1年前どころか数か月前までの主義や主張が全然変わってしまっていることは珍しくない(もちろん、変わらない部分もあるのだけど)。また、自分が過去に書いたものを読むと、現在の考えとは正反対の主張をしていることも多い。そうすると、より根本的な疑問として、30年前の自分と10年前の自分、今の自分、そして15年後の自分は、仮に記憶が継続しているとしても、本当に同じ人物なのか?という疑問がある。さらに仮定を進めて、もし記憶の(もっと)大部分が毎年失われるとしたら、何をもって同じ人物だというのだろう?これを上記の問いに当てはめると、Noつまり「精神的な意味での『自分』は、それほど連続的でも不変でもないので、それは不可能である」ということになる。
いやもちろん、社会生活を営む上で全面的に後者の立場をとったら、1年前の悪事の責任をとらなくてもいいとか、過去に締結した契約や約束を守らなくてもいいとか、将来のために努力するのは無意味とかになってしまって、大混乱になっちゃうので困るでしょということはわかるのだけど、他方、前者の立場をとるとどうしても避けられない問題は、終始一貫している「自分」のすべてが、死によって終了してしまうという点だ。それは耐えがたい恐怖である。
なので、その都合の悪さというか恐怖を和らげるためといってもいいが、自分は年齢とともに後者に傾いてきたわけで、この考えを極端に推し進めて「きのうの自分と今日の自分と明日の自分は、記憶はつながっていても別人」と考えれば、死は近未来のどこかにある自分の「結果的に最終日となる、その日の自分」を終わらせる出来事にすぎず、ずいぶん気分が楽になる。
しかし、それで割り切れるはずもないことは上に書いたとおりで、それ以上考えを深めないままYesとNoをあいまいに両手に抱えているところを目がけてこの剛速球が飛んできて死球で昏倒した次第。
ということで、まだ6月だけど『ののはな通信』が今年のベストワンに決定。
※ そっち方面に詳しい方は気づかれたと思うが、後者は私のオリジナルでもなんでもなく、イギリスの哲学者デレク・パーフィットの影響というか受け売りである。自分の思想の中心部分がオリジナルでないとは何事か、と怒られそうだが、自分で考え抜く力がないので仕方がない。
(6.20追記)
本文最後の4行、それもこのストーリーのあとにこの4行を持ってくるのは、三浦しをんにしかできない技なのでは。難しい言葉を一切つかわずこの4行を書ける力がすごい。あっこれは電車で読んではいけないやつだと気づいた時にはもう手遅れ。
この小説家と同時代に生きていて、新作を楽しみにできることが幸せ。
津村記久子『ディス・イズ・ザ・デイ』(朝日文庫、2021) [本と雑誌]

「この世にたやすい仕事はない」(2018)に出てきたフットボールチーム「カングレーホ大林」が現れてちょっと驚く。名前の由来がわからないが、なんで「大林」だけ架空の地名なんだろう。また、地名の単位が小さければ小さいほど、そこから想起されるイメージが具体的になるので、ストーリーもリアルになりやすいような気がする。たとえば、旧国名でもある「土佐」「出雲」と、「川越」「遠野」「白馬」などのスコープの違いは明らかで、どちらがいいという話ではなく、読み手が受ける印象が異なったものになってくる。
第10話「唱和する芝生」が最も楽しく読めた。ここに出てくる曲のほとんどを知らないが、それでも楽しく読める。この第10話の主人公は、それほど重い屈託を抱えているわけではなく、この点が津村作品のコアなファンには物足りないと感じられるかもしれないが、シンプルなストーリーのなかに、人がなぜ生きていけるかの示唆があるように思われる。
また、私はフットボールを全然知らないが、だからこの本が楽しめないということは一切なかった(知っていたらもっと楽しめる点があるのかもしれないが)。だから、フットボールを題材にしているとはいえ、これを「サッカー本」と呼ぶことにはちょっとためらうものがある。それは、「この世にたやすい仕事はない」を「お仕事小説」と呼ぶことがためらわれるのと同じだ。
ベン・モンゴメリ『グランマ・ゲイトウッドのロングトレイル』(浜本マヤ訳、山と渓谷社、2021) [本と雑誌]

これは読まないと。
スルーハイカーがほとんどいなかった時代に、「なぜ」彼女が歩こうと思ったのか。本書はこの点を考えようとしていて、確かにこれは大きなテーマになるのだけど、今となっては確かめようがない。さまざまに込み入った事情をかかえた彼女の人生も、理由になりそうではあるが、理由と断定できるようなものではない。
それよりも、唯一確実なことは、彼女が歩くことをいかに愛していたかということで、それがスルーハイク完遂後の思わぬ展開(正直、こういう展開は予想していなかった)から読み取ることができる。だから、本書を「歩くことの理由探し」の本として読むと、物足りなさを感じるかもしれないが、歩くことの楽しさに気づいた女性の物語として読めば、ソローやエマーソンを連想したりもして、とても楽しめるのではないだろうか。
森博嗣『喜嶋先生の静かな世界』(講談社文庫、2013) [本と雑誌]

最後の10ページで「?」。
この終わりかたはないだろう。
仮にこの終わりかたがあるとしたら、これはスピカの物語なのだ、と理解するしかないが。
丸山正樹『慟哭は聞こえない デフ・ヴォイス』(創元推理文庫、2021) [本と雑誌]

本作はシリーズ第3作にあたるが、第1作、第2作と同様、フィクションでありながら、「それは知らなかった」と気づかせてくれることが多々ある。
また、第3話「静かな男」の完成度が際立って高く、これだけでも読む価値がある。
シマダスの20年(「日本の島ガイド SHIMADAS」日本離島センター、2019) [本と雑誌]

はじめて読んだ「シマダス」は、2つ前の版(1998年版)だったと思うのだけど、神保町のすずらん通りにあった「書肆アクセス(地方小出版流通センター)」で購入した記憶がある。「シマダス」は読み物ではないけど、次の旅行先探しとして、または、まだ行ったことのない島のカタログとして、楽しく読んだ記憶がある。
その新版が15年ぶりに出たと聞き、即座に地元の書店に注文して入手。98年版から数えれば20年以上になるが、しかし、98年版を読んだときに感じたワクワク感のかわりに、離島がおかれた苦境のようなものが強く感じられ、読むのがつらかった。
いちばんつらいのは、島の人口(平成27年国勢調査)の横に、5年前の国勢調査との比較(増減)のカッコ書きがついているのだが、それが、どこかの家電量販店ではないが、1割、2割減は当たり前なのだ。わずか5年で。考えてもみてほしいが、都会だろうと山村だろうと、自分の町内で5年間に2割も人が減ったら、コミュニティーが維持できるものだろうか。おそらく、できないのではないか。離島は、そこに住む人々の結束が固い地域であると思われ、それがため、かろうじて維持されているのかもしれないが、いま住んでいる人々がいなくなったら―それは、そう遠い先のことではない―どうするのだろうか。移転の自由がある以上、誰かに離島に住むことを強制することはできない。それどころか新自由主義者ないし市場原理主義者は、経済合理性の観点から、むしろ島が無人になることを歓迎するかもしれない(コンパクトシティとかいう議論にもその種の胡散臭さを感じるのだけど、離島となると、もっと直截に問題になりますね)。結果的に、国土の一部を事実上見捨てることになるわけだが、それでよいのですかね。
それはともかく、旅行者であり続けたとしても離島に夢や幻想ばかりを抱いているわけにいかないので、離島がおかれた現実を冷静にふまえながら、先方の事情が許す範囲で楽しく遊ばせていただくのがこれからの目標ということになる。

