児玉聡「オックスフォード哲学者奇行」(明石書店、2022) [本と雑誌]
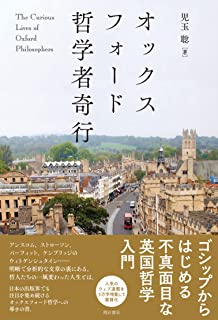
何の面識もない過去の哲学者たちの風変りな言動に、どうしてこんなにワクワクするのだろう。単にワクワクするのみならず、もしこうした哲学者たちのチュートリアルを受けたとしたら、おそらく3秒で粉砕されるだろうけど、自分の学生生活はもっと違ったものになったのではないか(いや、古文書室で過ごした2年間も自分にとっては限界までやり切ったとは思うし、もっと何かできたはずなどと考えるのは不遜なのだが)と考えると、ワクワクを超えてゾクゾクするものがある。
ちょっと目を惹かれたのは、その黄金時代?に、日本からの留学生が1人いたという事実。それも、アンスコムにチュートリアルを受けていたというのだから只事ではない。この方は、帰国後にどうされているのだろうか…と調べてみたら、ライプニッツ研究の第一人者として、慶応義塾でも教えておられたのですね。
あとがきのそのまた最後に、先日読んだばかりの「マルクス・アウレリウス」の著者南川高志先生の名前が出てきてびっくり。考えてみれば京大文学部つながりなので当然なのだけど。
ところで、奇行種って何?
第179回深夜句会(4/13) [俳句]
177回は急用で欠席、178回はこれまた急用で投句だけして早退したので、3か月ぶりの深夜句会。
(選句用紙から)
待ちぼうけの駅に菜の花揺れ遊ぶ
携帯電話のない時代、「待ちぼうけ」はときどき起こる事故のようなもので、そのために駅には伝言板が置かれたりしていたのだけど、その駅というのが都会のターミナル駅ではなく、菜の花が咲いているような場所にあるという。そうした場所に住んでいる人の話なのか、あるいはそうした場所を訪ねたあとで駅での待ち合わせがうまくいかなかったのか定かでないが、それにもかかわらず、菜の花は何もなかったかのように揺れ「遊んで」いる。春うらら。
ぽつかりと青空のあり春疾風
ぽっかりと、に議論があるかもしれないが、春の嵐で雲が飛び去っていくさなかに、ふと雲の隙間に青空が覗く、その青空が、冬の空でもなく夏の空でもない、春の色をした青空だ、という句。嵐そのものの様子というより、その嵐の途切れたところに見えている春の空を詠んでいるところが面白いと思う。
チューリップ雨の軽さに傾ぎけり
雨の重さに、でなく「軽さに」傾ぐという表現が狙ったものと思うが、しかし眼前の事実でもあって、そこがこの句の手柄なのだと思う。くどく説明すれば「降っているのは春の細かい軽い雨であって、たたきつけるような降り方ではないのだけど、その軽さにもかかわらず傾いだ」ということなのだろうけど、俳句なので説明は不要。
寛いで家のやうなる花筵
花筵がわが家のよう、という感じが面白い。ちょっとよその花筵に出かけてお相伴に預かって、でもまた戻ってくる。花筵に何人かの、気の置けない仲間か家族がいることが読み取れる。また、「家のやうなる」で相対化されていることから、広い公園のような場所であって、ほかにもたくさんの花筵が広がっている感じか。
(句帳から)
レモン色のデイジー心昏き日も
花蘇芳三代続く診療所
公園のここな小道の濃山吹
山吹の山吹色の開花かな
諸葛菜東中野に至る土手
花蘇芳日ごとその色褪せてゆく
町宿の奥の暗がり春深し
(選句用紙から)
待ちぼうけの駅に菜の花揺れ遊ぶ
携帯電話のない時代、「待ちぼうけ」はときどき起こる事故のようなもので、そのために駅には伝言板が置かれたりしていたのだけど、その駅というのが都会のターミナル駅ではなく、菜の花が咲いているような場所にあるという。そうした場所に住んでいる人の話なのか、あるいはそうした場所を訪ねたあとで駅での待ち合わせがうまくいかなかったのか定かでないが、それにもかかわらず、菜の花は何もなかったかのように揺れ「遊んで」いる。春うらら。
ぽつかりと青空のあり春疾風
ぽっかりと、に議論があるかもしれないが、春の嵐で雲が飛び去っていくさなかに、ふと雲の隙間に青空が覗く、その青空が、冬の空でもなく夏の空でもない、春の色をした青空だ、という句。嵐そのものの様子というより、その嵐の途切れたところに見えている春の空を詠んでいるところが面白いと思う。
チューリップ雨の軽さに傾ぎけり
雨の重さに、でなく「軽さに」傾ぐという表現が狙ったものと思うが、しかし眼前の事実でもあって、そこがこの句の手柄なのだと思う。くどく説明すれば「降っているのは春の細かい軽い雨であって、たたきつけるような降り方ではないのだけど、その軽さにもかかわらず傾いだ」ということなのだろうけど、俳句なので説明は不要。
寛いで家のやうなる花筵
花筵がわが家のよう、という感じが面白い。ちょっとよその花筵に出かけてお相伴に預かって、でもまた戻ってくる。花筵に何人かの、気の置けない仲間か家族がいることが読み取れる。また、「家のやうなる」で相対化されていることから、広い公園のような場所であって、ほかにもたくさんの花筵が広がっている感じか。
(句帳から)
レモン色のデイジー心昏き日も
花蘇芳三代続く診療所
公園のここな小道の濃山吹
山吹の山吹色の開花かな
諸葛菜東中野に至る土手
花蘇芳日ごとその色褪せてゆく
町宿の奥の暗がり春深し

