『カササギ殺人事件(上・下)』(2018、創元推理文庫) [本と雑誌]
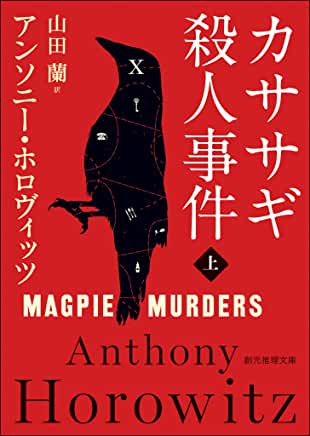
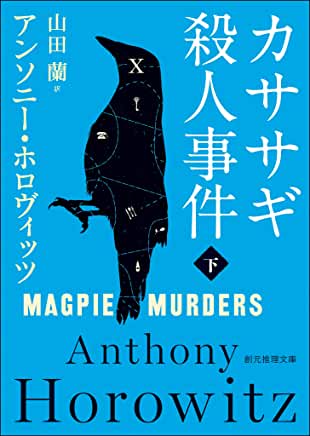
こ、これは…
ミステリの知識がないので、この本のしかけにすっかりはまってしまって、下巻に入ってからは「?」の連続だった。ミステリにはまだ、こんな可能性があったのですね。すごい。
ただ…
犯行の原因を「ある種の資質」に求めるこのストーリーは、どこまで説得的なのかという疑問が。「ある種の資質」って、それ以上深掘りしようがないというか、検証不可能なものなので、読み手としては少々持て余してしまうのだけど。
中島京子『樽とタタン』(新潮文庫、2020) [本と雑誌]

出張に持参した本を往路で読み終えてしまい、現地の本屋さんの新刊台から選んだ一冊。雨が降る寒い日だったのに、復路の電車が暖かく感じたのは、この本のおかげかもしれない。
いわゆる「いい話」とはちょっと違うのだけど、
・こどものころのトモコの視点
・大きくなって物書きになったトモコの視点
・作者すなわち中島京子さんの視点
が巧みに混同というかソフトフォーカスで描かれていて、さらに一つ一つのエピソードも、小説の中でさえも現実であるようなないような、ふわっとしたファンタジー風味になっている(軽いホラー風味といってもよいかもしれない)。この味わいは、単なる懐古とはまったく異なるので、誰でも共感できるとまではいえないだろうが、「過去って、べったりと懐かしいものではなく、そういう不思議な面があるよね」という了解ができる人なら、文句なく楽しめると思う。最後にトモコがその場所を訪ねるくだりは、そっけなく書いてあるだけにいっそう思いをかきたてる。
著者の他の作品を読んでみたくなる一冊。
小池昌代『弦と響』(光文社文庫、2012) [本と雑誌]
「本の雑誌」10月号に、弦楽四重奏団のラストコンサートを描いた小説として紹介されていたので、さっそく読んでみたのだけど…
弦楽四重奏曲に限らず、デュオでもトリオでも、それがたとえ初心者のアンサンブルでも、楽器と楽器とが音を重ねることの素朴な喜びみたいなものが必ずあるのだけど、どうしたことか、この小説にはそれがあまり感じられないのが残念。たまたま題材が弦楽四重奏だっただけ、といったら言い過ぎだろうか。ひとつひとつのエピソードは楽しくて、よく取材されていることが窺われるのだけど。
先崎学『うつ病九段』(文春文庫、2020)【一部ネタバレ注意】 [本と雑誌]

まだ7月だが、今年のベストワンはこれになるのではないかと。「なるほど」の連続。
自分や家族のうつ病についての経験談は数限りなくあるけれど、これは出色の一冊。その理由は、
・もともと筆の力のある人なので、「心の状態」というむずかしいことを、リアリティーをもってうまく説明できていること
・回復の過程が棋力を通じて測定(検証)可能だという観察が、とても説得的であること
の二点。
一点目については、著者自身が「エピソードが少なすぎる」(p.162)と書かれているが、全然そんなことはない。シャワー室でシャワーを浴びて「かすかな心地よい感覚にすごく懐かしいものを感じた」(p.32)箇所とか、回診中の教授とのやりとり(pp.53-4)とか、後輩の何気ない一言に感激する(p.74)とか、読んでいるこちらが思わずふうっと息をついてしまいそうな迫力がある。ついでに、ジンギスカン屋で隣の女性から布教されてしまう場面(p.121-2)なんかも、やっぱりそうだよね、と思わせる。角田光代さんが「インタビューなんかじゃなく、自分で(この本を)書いてください」(pp.161-2)と強く勧めたのがよくわかる。
ただ、腰巻きに使われているエピソード(p.98)は本題からちょっと外れているように思われ、編集者がなぜこれを使おうと思ったのか疑問が残る。
二点目については、病院の看護師さんと将棋をさすエピソード(pp.47-8)を振り出しに、そこから長い長い時間をかけて回復していく過程がきわめて具体的に(ここ重要!)綴られており、納得がいく。これが例えば、事務の仕事だったら、出来栄えが向上したり劣化したりしても、認識も測定もなかなか難しいところ、本書のように書かれていれば、将棋をまったく解さない自分でさえ、なるほどそうなのかと思う。
また、この経過を読んでいると、人間が「社会」に属して生きている動物だということを痛感する(マギー、聞いてる?)。
余談。この本では「ヒマ(退屈)と感じるかどうか」が回復を示す物差しのひとつとされているし、「ヒマを感じないというのは、うつの症状そのものといってもよいのではないだろうか。」(p.63)と書かれている。また実際、時間の経過とともに退屈を覚えることが多くなり、「これが脳にエネルギーが溜まってきた証拠である」(p.134)とも書かれている。これと裏返しのように、著者が発病直前まで大変な激務の渦中にあって、それが落ち着いたところで病気が始まったことも、示唆的である。激務かどうかは別として、ヒマを感じるかどうかという物差しだとしたら、勤め人の多くは、もう何年も、ヒマだと感じたことがないのではないだろうか(そんなことはないか。でも自分についていえば、2005年ごろからもう15年ぐらい、一度もヒマだと感じたことがないが…←これはこれで別の病気)。
本筋とは関係ないが、著者は自らについて「棋士のなかでは感性を大事にするほうであり」(p.152)と述べている。直感重視だとも書いている。ここでいう「感性」がどのようなものなのか、素人にはよくわからず残念なのだが、しかし例えば「将棋界は芸の世界で、先輩が後輩にこの世界の美しさ、存在意義とうを語りつぐ、あるいは姿勢を教えるものだという伝統があり、私もそういう教育を受けて育った。しかしいつごろからかそうした風潮が薄れつつあり、私は常々不満に思っていた。」(p.102)という物言いからは、どちらかといえば規範意識の強い、俗にうつ病になりやすいとされる性格のようにも思われるのだが。
(9.20追記)
著者に向かって精神科医がこう言う場面がある。「医者や薬は助けてくれるだけなんだ。自分自身がうつを治すんだ。風の音や花の香り、色、そういった大自然こそうつを治す力で、足で一歩一歩それらのエネルギーを取り込むんだ!」
俳人だったら、これを読んでおおっと思うわけですね。風の音や花の香りや色を取り込むといったら、俳句を詠むときにやっていることそのものではないですか。そうすると俳人は、うつ病になっても回復しやすいのだろうか。いや逆に、そういう習慣があるにもかかわらずうつ病になってしまうとしたら、重いうつ病になってしまうということなのだろうか。
川端康雄『ジョージ・オーウェル ー「人間らしさ」への讃歌』(岩波新書、2020) [本と雑誌]

ベストワン確定などと断言してしまうと(前の記事)、その直後にこういう本が現れて、しまったと思うわけで。
オーウェルというと、とかく「1984」の著者という部分が前景化してしまいがち(これは仕方ない)なことから、それ「以外」をきちんと拾って生涯と作品を追っていく試みは、たいへんありがたい。著者は、平凡社ライブラリーの「オーウェル評論集」や岩波文庫の「動物農場」の訳者でもあり、オーウェルについてまとめて講義してもらうには最適の先生のひとりだろう。
全体のストーリーとも関係するが、オーウェルが制作したBBCのインド向けラジオ放送を、海軍軍属としてジャワ島で働いていた鶴見俊輔が聴いていたというエピソード(pp.172-3)が胸アツというか、すばらしい。オーウェル自身は、こんな放送誰も聴いてないだろうと思っていた(仕事自体が、ムダな仕事だと考えていた)らしいが、全然そうではなかったのだ。私たちは、オーウェルの著作から直接に影響を受けるだけでなく、鶴見俊輔の多方面にわたる業績を経由する形でも影響を受けているとすれば、それは素晴らしいことではないかと。
オーウェルが最後までこだわったdecencyというキーワードは、日本語化するのが難しいことばだが、イギリスの社会を念頭におくと、とても納得できるというか、思想A対思想Bみたいな捉え方でなく、その他のどれでもない(どれとも比較のしようがない)decencyという物差しが、とてもイギリス的だと思う。この本にも出てくる"England, Your England"の、大上段に構えない静かな物言いが、とても好きだ。
ジュラ島への転居、そして死が近づいてくる最後の2章ぐらいは、あえて淡々と書いてあるだけに涙なしには読めない。こんな経過があったのですね。それにしても、なぜストレプトマイシンが効かなかったのだろう?他に治療法はなかったのか?
最後に、腰巻に「オーウェルの憂えた未来に/私たちは立っているのだろうか」とあるのが意味深なのだけど、立っているどころか、その憂えた未来に嬉々として突進してい(以下自粛)
池澤夏樹・池澤春菜『ぜんぶ本の話』(毎日新聞出版、2020) [本と雑誌]

本好きな人なら誰しも、15歳ごろまでに好んで読んだシリーズとか作者があるはずだが、この二人がどんな本を読んできたのか、どの本のどんな細部に惹かれたのか、それを聞くだけでも楽しい。たまに自分と同じ経験をしていたり、自分の好きな本を評価していたりすると、なお嬉しかったりする。
他方、「そんな本があるのか!じゃあ注文しよう」となってますます本棚がふくれあがる悪夢が…
第7章の「読書家三代 父たちの本」(この7章だけでも、この本を買う価値がある)に続いて、巻末に「父の三冊」と題するエッセイが置かれ、そこで池澤夏樹が福永武彦の、また池澤春菜が池澤夏樹の三冊を選んでいるのだけど、それが一冊たりとも、自分(藪柑子)が考える三冊と重なっていないのが面白い。
小野寺史宜『食っちゃ寝て書いて』(角川書店、2020) [本と雑誌]

大活劇が好きな人には、何も起こってなくてつまらないと言われそうだが、一見何でもないことを積み重ねていって、人の深いところにある何かが少しずつ見えたり変わったりし始めるところがいい。高浜虚子が「ボーッとした句やヌーッとした句を希求する」と公言していたことを思い出す。
ただし、腰巻きの「大人の青春小説」「再生の物語」という惹句はいただけない。そういうどぎつい表現や、これを「再生」と捉えるような思考を否定したいのが、横尾成吾の本領(この本の主旨)なのではないかしら。たとえば、横尾と弓子のこんな会話。
(以下引用)
----------
「限りなく拒否に近い保留、くらいには思ってていいのか?」
「拒否って言葉はキツいわね。だったらただの保留でいいわよ」
「永遠の保留だ」
「永遠の保留。それ、小説のタイトルにすれば?」
「カッコ悪いよ。永遠なんて言葉、おれ、小説で一度もつかったことないんじゃないかな。少なくとも、そんなふうにカッコをつける感じではつかってない」
「そこが横尾の小説のいいとこだよね。わたし、横尾と知り合いではなかったとしても、横尾の小説は読んでたと思うよ。好きになってたと思う。」
----------
(以上引用終わり)
また、終わり方も(面白い工夫があるが)やはり何も大事件は起こらないながらにいい終わり方でほっとする。こういう着地のしかたもあるのですね。
ジャン=クリストフ・リュファン『永遠なるカミーノ フランス人作家による〈もう一つの〉サンティアゴ巡礼記』(今野喜和人訳、春風社、2020) [本と雑誌]

スペイン巡礼の道を歩いた手記はたくさんあるのだけど、その多くは、ガイドブックの劣化コピーとは言わないまでも、単なる行動記録またはお小遣い帳になってしまっていて、「書いてあることは本当だと思うけど、なぜこの道を選んだのかとか、自分の内面がどう変化したのかとか、そういう深い部分がわからない」という不満があった。
そこへこの一冊が登場。こういう本を待っていました。巡礼を肯定的にとらえつつ、同時に、その巡礼自体を批評してやまない(時として、それは同時に行われる)ところがいい。もっとも、華やかな話はほとんどないので、長い距離を歩くこと自体が大好きでないと、入り込めないかも。
しいて残念な点を挙げるとすれば、エキゾチックなものや土俗的なものを「仏教的」のひとことで片づけてしまうところ。著者のような知識人でもこんなものだろうか。私にはむしろ、ここで「仏教的」と表現されたものの多くが、東方正教会的に感じられるのだけど。
(8.13追記)
本書の至るところに、気のきいたというか、そうだよなあと思わせる説明があるので、いくつか引用してコメントを。
(以下引用)
----------
私のしわくちゃで汚れて日に灼けたクレデンシャルを見ていると、祖父が戦時中の捕囚生活から持ち帰ってきた紙切れー配給券や診療票などーを思い起こす。抑留者にとってそれは無限の価値があり、どれだけ大事に身につけていたかと想像するのである。カミーノがこれと異なるのは、サンティアゴ巡礼が罰ではなう、自ら望んだ試練だということである。少なくとも本人はそう信じている。ただし、その考えは実体験によってすぐに覆される。カミーノを歩いたのは何ものかに強いられた結果だと、誰もが遅かれ早かれ考えるようになる(……)人は自由の精神を持ってサンティアゴに向けて旅立つが、ほどなくして自分も他の人々と同じく、単なる巡礼徒刑者さと思うようになる。(p.15)
巡礼路の最後の部分しか歩かないくせに、厚かましくもクレデンシャルを携えている連中のことを、真正の巡礼者たちはペテン師だと考える。フランスやその他のヨーロッパの国々から出発した巡礼者たちの、いつ終わるとも知れぬ旅と、何日間かだけ歩くウォーキングツアーが比べられるものか! こうした反応の中にはいくぶんスノビズムがある。けれども、カミーノを歩むにつれて、この考え方にもそれなりの真理があることを人は理解する。というのも、「本物の」徒歩巡礼者を作るには、時間が本質的な役割を果たすと認めざるを得ないからだ。カミーノは、〈時間〉が魂に働きかける錬金術である。それは一瞬で片付けることも、大急ぎでこなすこともできないプロセスである。何週間も徒歩で歩き通した巡礼者だけがそれを体験する。(p.17)
コンポステーラはキリスト教の巡礼ではなく、この事実を人がどう受け止めるかに応じて、それ以上のもの、あるいは、それ以下のものである。本来的にいかなる宗教にも属しておらず、実を言えば、中に込めたいものを何でも込めることができる。何かの宗教に近いとしても、宗教の中で最も宗教的でない宗教、神について何も語らないが、神の存在に人間を近づけてくれる宗教。コンポステーラは仏教的な巡礼である。思索や渇望から苦悩を解放し、精神から高慢を、身体から苦痛をすべて取り除く。事物を包む硬い殻を消し去り、事物を我々の意識から隔てる。自我を自然との共鳴状態に置く。(p.149)
ベルギーの若者は、巡礼者をほとんど見かけない自分の国とフランスを歩いたときのことを話してくれた。この二一世紀の初めに、至る所で思いがけず熱い歓迎を受けたという。村人たちは、果物や卵を頒けてくれて、コンポステーラで自分のために祈って欲しいと頼んだ。テレビとインターネットの時代に、巡礼者は思想や人間の交流を体現し続けている。メディアが代表し、警戒心やさらには不信さえ引き起こすバーチャルで速成の事柄と正反対に、巡礼者の動きは確かなものとして存在する。それは靴底にこびりついた泥や、シャツを濡らす汗によって証明される。信頼に足る存在である。(pp.182-3)
-----------
(以上引用終わり)
同じ道を歩いても、考えることが人ごとに異なるのは当然なのだけど、カミーノが多くの人を惹きつける理由を最大公約数的に説明するとしたら、こんな感じになるのではないかと。
(8.23追記)
著者が歩いた「北の道」にくらべて、「フランス人の道」の盛況ぶりというか混雑ぶりが強調されているので、ハイシーズンに「フランス人の道」を歩くのはやめたほうがいいのだろうかなどと考えてしまう。
君塚直隆『エリザベス女王』(中公新書、2020) [本と雑誌]
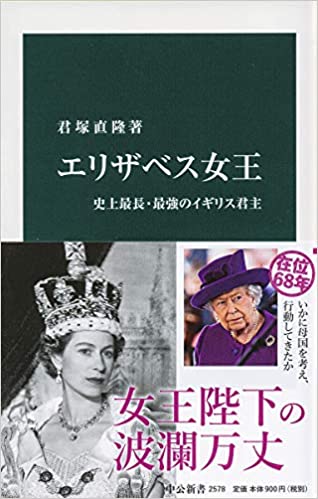
映画「英国王のスピーチ」(2010年英豪米、トム・フーパ―監督)には、子どものころのエリザベスがちょっと出てくるのだけど、そこで描かれたお父さん(ジョージ6世)の生真面目な性格を、女王陛下はよく受け継がれたのだなあと思う。
自分が物心ついた時には、すでに女王陛下は女王陛下だったわけで、それから数十年、王侯だから当然のように思っていたが、常に同時代の人物として人々から意識され続けるのは、とても特異なことだと改めて実感する。例えば、ごく最近の首相であるメージャーやブレアでさえ、今どこでどんな活動をしているかは(少なくとも自分のような素人には)遠い世界の話なのに、なんとチャーチル首相の時代から70年近く第一線にいるということ自体、想像を絶することだ。また、諸外国の王室のような、高齢を理由にした退位を全くお考えでないことがわかったが、その理由も、この方らしいなあ(ついでに言えば、この方がそう言うならそうするしかないだろうなあ)と思わせる。
発見として、日本にいるとなじみのない「コモンウェルス」という紐帯が、イギリスにおいては(当たり前だけど)重要なのですね。たしかケンジントンのどこかに、コモンウェルス博物館みたいなものがあって、一度だけ拝見した記憶が。サッチャーがコモンウェルスを毛嫌いしたというのが、さもありなんというところ。なにしろ、国家と個人はあるけど社会は存在しないと言い放った人間だからして。逆に、ブレアがコモンウェルスに無関心だったというのが意外。
新書って、専門家が一般人向けに書いてくれるという性質上、本来なら何冊もの専門書を読み、記述を突き合わせて理解しなければならないことを、煎じ詰めて書いてくださるので、すごく理解した気になって気持ちがよい。しかし、じゃあ自分もその道の専門家になれるかというと、これは当然、一生かけてもなかなかその域には達しないわけで、この「理解した気になる」のが怖いところ。それでも、この先生の大学院のゼミに入って修論書いてみたいなあなどと思う(大変だけど楽しそう)。テーマは…どんな一次史料が発掘できるか次第だろう。ヴィクトリア女王の日記同様、エリザベス女王の日記も、後世の研究者にとっては超重要な一次史料になるのでしょうね。
宮下奈都『スコーレNo.4』(光文社文庫、2009) [本と雑誌]
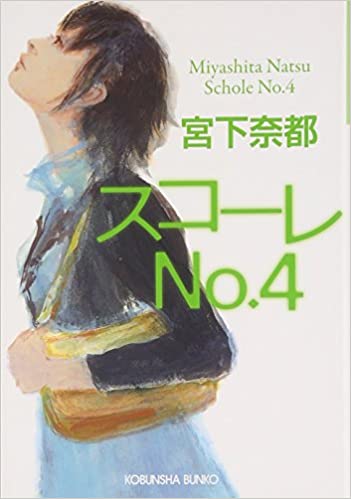
『羊と鋼の森』を読んで、もっと他の作品を読んでみたくなったので。
形容詞や副詞でごまかさない丁寧な描写があり、他方で、意表をついた描写がある。そのリズムが、いわば「宮下節」ともいうべき心地よさを生んでいるように思う。例えば、
(以下引用)
広くなったり細くなったりしながら緩やかに流れてきた川が、東に大きく西に小さく寄り道した挙げ句、風に煽て(おだて)られて機嫌よくハミングする辺りに私の町がある。
(以上引用終わり。p.13)
なんと自由自在な描写。しかもこの川の描写が、最終章までのあちこちで再現されて効果をもたらしているのだ。いいですね。むろん、自然だけでなく、人や物についても同様に、丁寧に描写されていく。それが説明に陥らない点も含めて、ちょっと俳句を連想する。
ストーリーについていえば、作者の意図とは別に、仕事について描いた「No.3」に心惹かれるものがあった。「No.4」が「小説を読んでいる」という感じを受ける(もちろん、とても感じのよい小説ではあるのだけど)とすれば、「No.3」にはそういう感じがなく、すっと入りこめるのだ。もっとも、この点は、読者の年齢や性別や興味によって全く異なるかもしれない。
田口久美子『増補 書店不屈宣言 わたしたちはへこたれない』(ちくま文庫、2017) [本と雑誌]
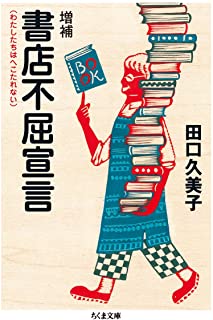
巣ごもり需要とか言い出すまでもなく、本は生活必需品と信じているので、地元の本屋が時間を短縮しつつも営業してくださっていることに深く感謝している。
本書を読み進めて「おっ」と思ったのは、某S氏のこの発言。
(以下引用)
「書店は私の恩人です。書店のためならなんでもやります。」
(以上引用終わり。73頁)
自分は「中の人」商法とか「元中の人」商法とかを信用しないのだけど、しかしこの発言は、S氏の一連の著作に通底するものとも整合するし、共感できる。
ブログは、たとえ自分のブログであっても、自分語りをする場ではないと思っているが、この件に関しては、「書店」のところを「書店と図書館と教育テレビ」と言い換えれば、そのまま自分にもあてはまるなあと愚考。もっとも、私にできることは、書店で本を買うこと以外には何もないのだけど。
もう一つ、著者が感じているAmazonの脅威は、皿回し又は租税法の観点からはもっと深い問題なのであって、そもそも法人税を払わない(しかも、同様のスキームを本邦の各社がつくることは事実上できない)のだから、市場での公正な競争が成り立たないわけで、大問題だと思うのだけど、日頃は市場原理主義をふりかざしている諸氏がどうして誰も問題にしないのか、もっときつくいえば、日本政府が相手にされていない状態なのにどうして不買運動が起こらないのか、不思議で仕方がない。
ということで、蟷螂の斧ですらないささやかな抵抗ではあるが、きょうもamazonで下調べをしてから、リアル書店で注文を出すのであった。
丸井英二編『わかる公衆衛生学・たのしい公衆衛生学』(弘文堂、2020) [本と雑誌]

1月に発売されたばかりの本。なんともタイムリーな出版になったわけですね。
特に楽しく読めたのが、
・第3章「人の特性によって何が違うのか」
・第5章「感染症の疫学」
・第8章「遺伝か環境か」
・第10章「健診・検診・スクリーニング」
・第15章「コミュニティ活動(地域活動)」
の5つのセクションで、わけても第5章と第15章は必読。
公衆衛生学を受講するのって、おそらく医学部とか看護学部の学生なのだろうけど、むしろ一般教養科目でこうした内容が教えられていれば、ある種の底上げになると思うのだけど。
にわか疫学者?が街にあふれる昨今、基本の基本を教えてくれるこういう本はとても貴重だと思う。
レベッカ・ソルニット 『ウォークス 歩くことの精神史』(東辻賢治郎訳、左右社、2017)【一部ネタバレ注意】 [本と雑誌]
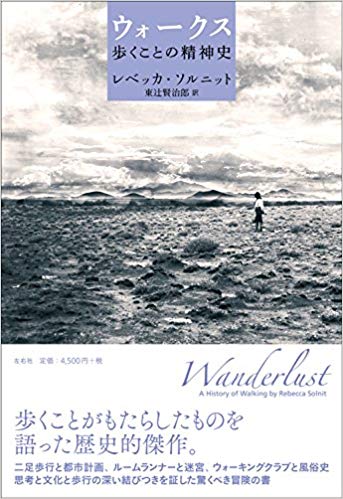
バックパッカーで、俳句が好きで、ロングトレイルを歩いたり100キロウォークに出場したりする人間にとって、こういう本は必修科目といってもよい。歩くことが体にいいとか悪いとかの効能の話ではなく(そういうhow to本のなんと多いこと!)、「歩くことはなぜ楽しいのか?」という根本的な疑問に、いくつかの楽しい仮説を提供してくれる一冊。
原題「wanderlust -- a history of walking」の「wanderlust」は、「旅行熱、放浪癖」といった意味なので、邦題の「精神史」は少々意訳気味。
本文だけで500ページを超えているが、歩くこと(正確にいえば、歩くこと自体を目的として、歩くこと)が、芸術の歴史上、あるいは社会史的にどう取り扱われてきたかが時代を追って説明されており、少しずつ読み進めればそれほど理解困難ではない。個別に「へぇ」と思った点をいくつか。
・巡礼の根底にあるのは、聖なるものはまったくの非物質的存在ではなく、霊性には地理があるという考えだ…巡礼は信ずることと動くこと、思惟と行為をむすびあわせる。聖なる存在が物質性と場所を備える、ということがこの調和の条件となるのはまことに理の通ったことだ。(p.86)
巡礼へとおもむくとき、人は世界との係累――家族、愛するもの、地位、あれこれの義務――を置き去りにし、歩く群れのひとりとなる。成就したことと捧げたものを除いては、巡礼者たちを隔てるものはない。(p.88)
・今日の読者にとっては、絵のような眺め、あるいは景色のための観光といったものの存在は、風景を好むこととおなじようにそれほど特筆すべきものとは思われないかもしれない。しかし、そのすべては十八世紀に発明されたものなのだ。(p.157)
・十九世紀における歩行の文芸の主流が歩くことのエッセイという形式だったとすれば、に十世紀にはきわめて長い距離を歩くことについての長々とした物語がそれに代わる。…わたしの知るかぎり、歩くこと自体を目的にした長距離の徒歩旅行について述べた最初の重要な文章は、ジョン・ミューアの『1000マイルの歩み』だ。一八六七年のインディアナポリスからフロリダ・キーズまでの旅が記されている。(pp.207-8)
・日本では、山は有史以前から宗教的に重要な存在だった…後になると、山に登ることが宗教行為の中核を占めるようになった。登山を特徴にした仏教宗派といえる修験道がそのことをはっきり示している…修験道は十九世紀後期に禁止され日本の宗教ではなくなるが、寺社や行者が消えることはなく、富士山はメジャーな巡礼地でありつづけ、日本人はいまなお世界的にももっとも熱心に山に登っている。(pp.240-1)
・わたしが出会ったイギリス人の多くは、土地の景観は彼らの受け継いだ遺産であり、自分たちにはその場に足を運ぶ権利があるという感覚をもっていた。合衆国ではそれよりはるかに私有財産が絶対視され、その正当化に寄与する存在として莫大な公有地がある。(p.270)
・しだいに周囲の風景との区別を失っていくうちに、庭はその必要性をも失っていたのだ。(p.151)
・田舎歩きの歴史が抱える大いなる皮肉、あるいは詩的な正義といえるのは、上流階級の庭園からはじまった嗜好が、巡りめぐって私的所有を絶対的にして特別の権利として攻撃するに至ったことだ。(p.277)
この本のなかにもフレッチャーの「遊歩大全」が出てくるが、読み終えて感じたのは、この「歩くことの精神史」が、「遊歩大全」の後継者(後継書?)だということ。
もうひとつ、自分が長いあいだ、旅するときに意識していた「地面の上を連続して移動する感覚」について、この本が同様の指摘をしてくれたことが嬉しかった。先に自分の持論を紹介しておくと、それはこのようなことだ。
自分の家から駅までの道順を思い描くとき、途中にある目標物、すなわち、大きな冠木門のある家とか、個人タクシーの営業所とか小さな喫茶店とか、パン屋とかスーパーとか、そうしたものが順番に配置されて、そのあとで駅に着く。それは、「頭の中の地図」に、それらの目標物が順番に(sequentialに)プロットされているからだ。駅で電車に乗って、大きなターミナル駅まで行くときにも、一軒一軒の家はわからないにしても、途中の駅は、頭の中の地図に従って順番に現れる。
ところが、飛行機で北米や欧州のどこかへ行くとき、そうした「頭の中の地図」の連続性はまったく失われてしまう。飛行機のドアが閉まってから、現地でもう一度開くまで、地図は空白なのだ。
で、この本ではこの点について以下のように説明している。
・わたしたちの知覚はそれ以来も加速されつづけているが、当時にすれば列車の速度は目も眩むものだった。それ以前の陸上移動の方法は旅人と環境を親密な関係でむすぶものだったが、十九世紀の精神にとって鉄道の速度は速すぎ、視界を掠めて飛んでゆく樹々や丘陵や町並みと視覚的な関係をむすぶことは不可能だった。此方と彼方との間にひろがる地表ととりむすんでいた空間的・感覚的な関係は希薄なものとなってゆく。その代わりに、二つの地点を隔てるものは時間だけとなり、それも留まることなく節減されてゆく。(p.432)
・近代以降の空間・時間・身体性の喪失に抗って歩きつづける者がいれば、それは対抗文化(カウンターカルチャー)あるいは副次文化(サブカルチャー)ということになるだろう。(p.447)
そうでしょうそうでしょう。こんな話をどっさり仕込んでから道を歩くと、それが駅から家までの道であっても、これまでより少し楽しくなるから不思議。
増田俊也『北海タイムス物語』(新潮文庫、2019)【一部ネタバレ注意】 [本と雑誌]

「こんな終わり方ってあるのだろうか」と衝撃を受けた「七帝柔道記」を読んでから3年弱、続編を待望していたが、これは続編といっても北大柔道部の話ではなく、お仕事小説である。ただし作者は、この作品にも「先輩」として登場する。もっとも、柔道か新聞紙面の整理かの違いはあっても、とことんやりぬくことがテーマになっている点はまったく同じである。
従って、普通に読めば、お仕事を通じて成長していく主人公が必死で仕事を覚え、独り立ちを果たす618頁以下のシーンがクライマックスなのだろうけど、私が感動するのはむしろ、そこから離れたところで行われる、ベテラン編集者どうしのこのような会話だ。単なるお仕事小説はあまり好きでないのだけど、こういう描写には惹かれる。
(以下引用。pp.523-4)
----------
「まだほとんど来てません。間に合うでしょうか」
「大丈夫だ。リードは三倍、本文は二倍でグリッド二段で流す」
「わかりました」
「横凸版は天地二十九倍、横百六十六倍、白ゴチベタ」
「了解です」
二人は数少ない言葉だけで通じ合い、互いのレイアウト用紙も見ないで一気に線を引いていく。そして凸版指定用紙にさらさらと見出しを書いた。(以下略)
----------
(以上引用終わり)
高度専門職がその全力を傾けて問題解決に挑む様子、もっと雑駁にいえば、なんだかよくわからないけど凄そうにみえるところに感動してしまうのだ。
似たような例で、印象に残っているのが、例えばアーサー・ヘイリーとジョン・キャッスルの共著『0-8滑走路』(清水政二訳、ハヤカワ文庫、1973)のこんな会話。
(以下引用。p.59)
----------------
二番目の男は彼の肩越しに首をのばして、タイプに打たれていく字句を読んだ。ベルで呼ばれた男は空港の管制官で、背が高く痩せていた。彼は一生を大空で過ごしてきた男で、自分の家の裏庭のように、北半球の飛行情況にくわしかった。いや、裏庭で育てる野菜には失敗しても、こと空となったら知らぬことはなかった。彼は通信の半ばですばやく数歩退って、振り向きもせず、部屋の向こう側にいる電話交換手にいきなり命じた。
「航空交通管制局をすぐ呼べ。それからウィニペッグのテレタイプ回線をあけておけ。優先通信だ」
--------------
(以上引用終わり。内容が古めかしいのは、1958年の作品であるため。)
書いているうちに、もう一つ思いだしたのがこんな会話。徳永進『臨床に吹く風』(岩波書店、1990)
から引用する。
(以下引用。pp.219-20)
---------------
「酸素二リットル吸わせて。胸部X線写真の正面と採血。レントゲン技師と検査技師を呼んで。酸素吸う前に血液ガスを。それから、カットダウンを右大腿でするから、その用意して。点滴の本体は五%ブドウ糖500mlで」次々に当直の看護婦さんに指示する。呼吸音を聞くと、両肺に喘鳴がある。血液ガスの採血をしようと両腕をみると、浮腫がすでにありあちこちで針のあとが内出血している。DIC(血管内凝固症候群)をおこしているのではないかと疑い、「プロトロンビン時間(PT)、ヘパプラスチン時間(HPT)、アンチトロンビン-Ⅲ(AT-Ⅲ)、FDPそれにフィブリノーゲンも採血して」と言う。
-------------
(以上引用終わり)
調子に乗って大引用大会になってしまったのだけど、しかし、何だかよくわからない表現に接して、よくわからないけど凄そうにみえることに感動してしまうのは、変といえば変な話で、これは自分に、権威らしきものに弱い面があるからなのかもしれない。くわばら、くわばら。
三浦しをん『あの家に暮らす四人の女』(中公文庫、2018) [本と雑誌]

いつものしをん節と少し違うような…と思いながら最後まで読んだが、あとがきで本書の成立事情を知って、ようやく得心がいく。あの古典的作品を下敷きにすると、こういう作品になるのですね…これは、モトをよく知っている人のほうが楽しめるかもしれない。
尾崎真理子『ひみつの王国 評伝石井桃子』(新潮文庫、2018) [本と雑誌]

自分の年代で読書好きの人間なら、石井桃子さん(以下敬称略)の文章に影響を受けなかった者は皆無といっていいだろう。「てまみ」「いやんなる!」「クフロ」「ご解消」…例をあげればきりがないが、藪柑子の貧しい語彙のかなりの部分は石井桃子由来のことばで占められている(分母が小さいので、さらに比率が高くなる)。
多くの著作から単純に導かれがちな「こども好きな児童文学者」とはまったく異なる石井桃子像、キャザーやファージョンやミルンに惹かれ、デモーニッシュなものをかかえた創造者としての石井桃子像を提起したところに、この評伝の最大の価値があると思われる。それを提示した第7章「晩年のスタイル」のなかの「私というファンタジー」(pp.614-621)は必読。むろん、読者がそれに同意するかは別ではあるが、私はかなり説得的に感じた。
また、仕事に関して妥協を許さない石井桃子の徹底ぶりは、求道者のようにさえ感じられるほどで、たとえばこんなエピソードが。
(以下引用)
-------------------------
石井は一九九〇年代半ばからアメリカの詩人アーサー・ビナード、イギリス人の語学研究者アラン・ストークに、一つひとつの単語の背後に潜む思いもよらない意味合いをつかむため、真剣に「英語のレッスン」を受けてもいた。特にストークとは五年間にわたって石井からの質問とそれに対する氏の回答の往還を繰り返し、これも段ボール箱いっぱいの書類が残されているほどで、その熱意は『今からではーー』の巻末の訳注にも滴っている。(p.622)
九十代にさしかかったその頃の石井は、「私、ようやく英語が少し、わかるようになってきた!」と周囲に自慢してみせることもあったらしい。(p.623)
-----------------
(以上引用終わり)
他ならぬ石井桃子に目の前で「私、ようやく英語が少し、わかるようになってきた!」なんて言われたら、絶句するしかないのですが。
この評伝のもう一つの大きな意味は、石井桃子の「通史」が初めて描かれたという点にある。これは、本書でも紹介されていることだが、ある時代を深く共にした友人でさえ、その前後の時代をまったく知らないというような、不思議なことなことが多々あって、それが系統的な(というのかな)理解を困難にしてきたという事情に由来する。
いうまでもなく、石井桃子は著名な人物なので、これまでにも数多くの「石井桃子論」が世に問われたことと思うが、本書は石井桃子論である前に、まずこれだけ多くの一次史料にあたり、かつ、本人や友人へのインタビュー(現在では不可能なインタビュー)を長時間にわたって行っていることから、これを超える評伝を著すことはかなり困難と思われる。
また、本書を読んでの傍論となるが、一次史料の最たるものとしての「書簡」の重要性を痛感する。往復書簡が残されていなかったら、本書を編むことはできなかっただろう。世代の問題にしてはいけないが、これだけたくさんの書簡を残した文学者は、これが最後になるのではないだろうか。
付言すると、石井桃子の評伝であることは同時に、日本の児童文学を築き上げてきた人々の列伝でもある。吉野源三郎や小林勇はそもそも出版人として著名だけれど、松居直、瀬田貞二、いぬいとみこ、光石夏弥、松岡享子、渡辺茂男、中川李枝子、山脇百合子…さながら「石井山脈」とでも呼ぶべきこの壮観!
(11.25追記)
本書では、瀬田貞二との交友についても紙幅を割いて説明している。瀬田貞二の勧めで、石井桃子が俳句を詠んでいたなら、どんな句になっただろうか、とふと想像する。散文でもあれだけリズムに気をつかう名手だから、他にはないような句を詠んだことだろう。
津村記久子『ワーカーズ・ダイジェスト』(集英社文庫、2014) [本と雑誌]

津村作品としては珍しく、主な登場人物の片方が男性。
仕事に関しては「そうそう、そういうことってあるよね」という率直な出来事の連続になるのだけど、仕事以外に関しては、何かが起こりそうでいて起こらない。男性と女性の会話も、読み手を試しているかのような不思議な会話で、「この場面でそのセリフですか?」的なはぐらかされ方。出てくる小道具も想定外というか、鍵盤ハーモニカですか。
人によっては、それを物足りなく感じるかもしれないが、自分には、このようなヤマもオチもない(仕事以外に関する)記述こそが、かえって、働く人、それも特別でない人の日常の記述として不思議な納得感がある。
津村記久子『この世にたやすい仕事はない』(新潮文庫、2018) [本と雑誌]

文句なしに面白い。小説ってこういうことができるのですね。
途中で「あれ?私はファンタジーを読んでいるのだろうか?」などと思わせておいて、最後にこんなふうに結末をつけるところは、小説の実作者でなくても感心せずにはいられない。
それ以上に面白かったのは、本書のあちこちに散りばめられているパワーワードで、能うかぎり紹介したいところだが、ネタバレを避け最小限にすると、
「一日に、A4の紙一枚以上の文章を読むと、虚脱感で使いものにならなくなる」(p.37)
「今のあなたには、仕事と愛憎関係に陥ることはおすすめしません」(p.187)
「疲れ果てている人のためのおかき」(p.195)←これ最高
「やんわりと私の仕事を乗っ取ろうとする人が現れたんですが」(p.227)
「人間の心の隙間にそっと忍び込んで、ぷすぷすと針で穴を開けていくような人々」(p.265)
「憎しみを不当に盛って投げつけてきている」(p.287)
これだけでも、この本を読みたくなりませんか?ならないか。
結末を書けないのが残念だが、ともかく『とにかくうちに帰ります』と併せて読むと、この作者の作品をもっと読みたくなることを保証する。
藤岡陽子『波風』(光文社文庫,2019) [本と雑誌]

文庫になったら読みたいと思っていた本で、かつ吉田伸子さんが解説を書かれているので、即座に購入。
この作者の、「どんな人にもその人の居場所があり、役割がある。ただし、それは自分で見つけなければならない」という信念のようなものは、どの作品にも共通している。だから、これを「お仕事小説」というのともちょっと違う。
それはともかくとして、作品と無関係に考えたことは、「自分が人生の最終局面で(おそらく)病院にお世話になるときに、どんなスタッフとどんなやりとりをすることになるのだろうか」ということだった。その時点でやりとりできる状態であるかは措いて、それがどのようなものであるかによって、最終的な満足感というのかQOLというのか、それが全く違ったものになることは確実と思われ、自分では選ぶ余地があまりないだけに、気になるところ。かといって、予約しておくわけにもいかないし。
津村記久子『とにかくうちに帰ります』(新潮文庫、2015) [本と雑誌]

オフィスを舞台にしたお仕事小説は山ほどあるけど、みんなで何かを成し遂げるようなスポ根物語ではなく(そういう小説には心底うんざりする)、また「オフィスあるある小話」とも違う(明確に違う)。そうではなく、いわば「オフィスで働いている人の心のありかたや仕事との向き合い方」を掘り下げる小説。
特に、標題作「とにかくうちに帰ります」を読むと、人は何を求めて生きているのか?などと考えはじめてしまう(ここで登場人物がめざす「うち」とは、家庭じゃなく「屋根」だったりするわけだが)。飄々とした風体のピッチャーが、スローカーブで油断させておいて剛速球を投げ込んでくる感じ…って全然説明になってませんね。この作者の他の作品も読んでみることに決めた。

