岸本尚毅『高浜虚子 俳句の力』(三省堂,2010)を読む [俳句]
「あとがき」によれば本書は,氏がこれまで『俳句』『俳句研究』などに寄稿されてきた文章をもとに構成したという。そうした成り立ちとも関係するが,一つの結論に向けて検討を積み重ねていくというより,虚子俳句のさまざまな側面を腑分けして,その特質を個々に指摘するといった趣になっているので,どこから読むことも可能。
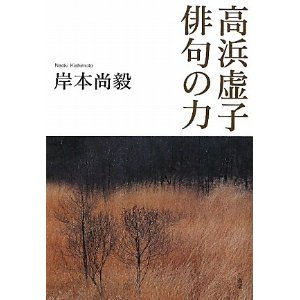
共感した点はいくつかあり,そのうち2つを書き抜いておくと,以下のとおり。
1.虚子の俳句を理解する上で,虚子小説の重要性を指摘していること。
逗子の虚子小説研究会に毎月参加していたころ(参加する時間があったころ),虚子の小説が執拗なまでに「自分自身を含めて,人の衰えたり死に絶えたりするさま」を追求しているのを読みながら,この小説世界は虚子の俳句とどういう関係にあるのだろうか,と漠然と考えていたが,氏の指摘するところでは,虚子は
・小説や戯曲は,運命に弄ばれる人間の悲惨を描く「地獄の文学」
・俳句や能楽は,地獄の文学以外の領域をに位置する「極楽の文学」
と棲み分けるべきものと捉えていたのではないかという(pp.136-7)。
地獄とか極楽といった性格づけもさることながら,この指摘のポイントは,俳句だけを取り出して虚子の俳句を論じるのではなく,小説家でもあった虚子が,小説と同じことを俳句でやる必要を感じなかったことを押さえるべき,という点にあると思う。むろん両者の根底には,事物を淡々と,温かくでも冷ややかでもなく静かに見据える虚子の目という共通点があって,その上に二つの柱が乗っているわけだが,虚子が小説で何を追求してきたかを見極めることは,小説以外で何を追求してきたかを間接的に示すものだということであって,これは納得がいく。
2.虚子の俳句を「帰納的」であると指摘していること。
虚子の挨拶句が巧みであることを捉え,「虚子の句は,虚子自身の個人的・私的な事情に則した句でありながら,同時に,万人の気持ちにすっと入り込んでゆける普遍性を持(つ)」「虚子の目には,「個々の事象の向こうに,物事の普遍的なあり方が見えていた。虚子は帰納法の達人だった。」と論じている(p.236)。
たしかに,虚子の句の「自由自在ぶり」とでも言いたくなるような振れ幅を目の当たりにしていると,それは多少なりとも帰納的であると納得せざるを得ない。そしてそれは,季題から出発するということとも符合することになる。
また,帰納的との指摘が成り立つということは,換言すれば(本書には何も書かれていないし,ここはそれを論じる場でもないが),「虚子以外の俳句のなかには,きわめて演繹的なものがある」ということだ。かなり意訳すると,個別から全体を見ていく帰納的アプローチは,個別のバラつきを容認しながらやがておぼろげに全体が見えてくる,という形をとるのに対して,全体から個別を決めていく演繹的アプローチは,はじめに「俳句とはこういうもの」と決めて,それに合致するように個別を作っていく,という形をとる。
むろん100%帰納法とか100%演繹法という俳人はいないわけで,みなその中間のどこかにいるわけだが,その結果何が起こるかというと,帰納的アプローチは,事物本位で何でも拾っていくので,全体をみたときに時々辻褄が合わなくなったりするのに対して,演繹的アプローチは,自分の理屈にはまる事実しか拾ってこないか,もしくは仕上げの段階で理屈に合わないものを除去するので,ブレはないけどつまらない,ということになるわけだ。無季の句をホトトギス雑詠欄に選び「この句の季題は?」と読者に尋ねられて「誤って無季の句を選びました。抹殺。」と返答する虚子の懐の深さ(『虚子俳句問答 理論編』pp.123-4(2001,角川書店))は,確かに帰納的としかいいようがない。
脱線ついでに無季といえば,「公園の茶屋の亭主の無愛想」という昭和16年4月4日の句(家庭俳句会)は,そのままホトトギス句日記→『句日記』(昭22)→『六百句』(昭和22)まで収録され,後に角川文庫から『五百句・五百五十句・六百句』(昭30)出版の際,ようやく「松の間の桜は幽かなるがよし」という句に差し替えられている(『虚子五句集(上)』p.250(岩波書店,1996))。融通無碍。
他方,自分なりにもう少し調べてみたい点が1点。
「俳諧から俳句への変化に伴い,座の文芸は活字の文芸へ,連衆の文芸は個の文芸へ,存問の文芸は独自の文芸へと変化したが,そうした近代の桎梏から俳句を解き放とうとしたのが虚子の「諷詠」であり,虚子の俳句はしきりに問いかけ,話しかける」という指摘(pp.213-215)は重要である。
その上でさらに「虚子門の俳人には,虚子という選者がいたから,いわば虚子にあてた諷詠に励むことができた。しかし虚子自身は,俳句の読み手としての大衆に対する不信感があり,選者として孤独だった」とされている(pp.222-30)。これはどうなのであろうか。
私たちは,虚子が最晩年まで熱心に句会に出席していたことを知っている。それは単に運動論としてあるいは選者の義務としてではなく,虚子自身が句会を愛好し,句会という形式の歴史とともにあったとさえいえる存在だったからでもある(この点は筑紫磐井「文学における虚子の位置」p.52以下(『俳句』編集部編『高浜虚子の世界』,2009,角川学芸出版)に詳しい)。
そこで考えておかなければならないのは,虚子といえども句会に投句すれば,互選に入ったり入らなかったりするはずだということだ。何が言いたいかというと,句会での互選の具合と,1年後の「ホトトギス」句日記(→単行本「句日記」→「五句集」という過程)との間にはどの程度の相関があったのか,いいかえれば虚子はどの程度互選の結果を考慮していたのか知りたいということ。言い換えれば,句会で「多くの賛同を得た句」とか「スルーされた句」という結果と,翌年の「ホトトギス」に載せる(ひいては「句日記」に載せる)ために選んだ句のあいだには,どの程度の相関があったのだろうということだ。
思いつきの域を出ないのだが,雑詠欄選者としては孤独だったとしても,句会の互選で入ったり入らなかったりの度合が若干でも「ホトトギス」句日記に反映されていれば,まったく孤独とはいえない,という考え方は無理だろうか。やはり句会の会衆も「俳句の読み手としての大衆に対する不信感があり」の内に含まれてしまうのであろうか。
そこで『虚子物語』(清崎敏郎・川崎展宏編,1979,有斐閣)と前掲『虚子俳句の世界』の2冊にあたってみる。選句に臨む虚子の考え方や,虚子選を聴くときの会衆の様子などは書かれているのだが,虚子自らの句が互選でどうなって,それがホトトギス「句日記』にどうつながっていくか,という記述は見当たらないように思われる。従ってこの点は当分,宿題にしておきたい。
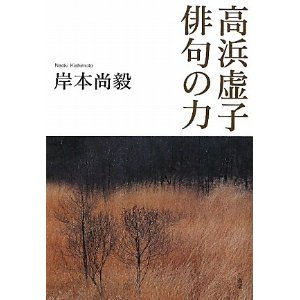
共感した点はいくつかあり,そのうち2つを書き抜いておくと,以下のとおり。
1.虚子の俳句を理解する上で,虚子小説の重要性を指摘していること。
逗子の虚子小説研究会に毎月参加していたころ(参加する時間があったころ),虚子の小説が執拗なまでに「自分自身を含めて,人の衰えたり死に絶えたりするさま」を追求しているのを読みながら,この小説世界は虚子の俳句とどういう関係にあるのだろうか,と漠然と考えていたが,氏の指摘するところでは,虚子は
・小説や戯曲は,運命に弄ばれる人間の悲惨を描く「地獄の文学」
・俳句や能楽は,地獄の文学以外の領域をに位置する「極楽の文学」
と棲み分けるべきものと捉えていたのではないかという(pp.136-7)。
地獄とか極楽といった性格づけもさることながら,この指摘のポイントは,俳句だけを取り出して虚子の俳句を論じるのではなく,小説家でもあった虚子が,小説と同じことを俳句でやる必要を感じなかったことを押さえるべき,という点にあると思う。むろん両者の根底には,事物を淡々と,温かくでも冷ややかでもなく静かに見据える虚子の目という共通点があって,その上に二つの柱が乗っているわけだが,虚子が小説で何を追求してきたかを見極めることは,小説以外で何を追求してきたかを間接的に示すものだということであって,これは納得がいく。
2.虚子の俳句を「帰納的」であると指摘していること。
虚子の挨拶句が巧みであることを捉え,「虚子の句は,虚子自身の個人的・私的な事情に則した句でありながら,同時に,万人の気持ちにすっと入り込んでゆける普遍性を持(つ)」「虚子の目には,「個々の事象の向こうに,物事の普遍的なあり方が見えていた。虚子は帰納法の達人だった。」と論じている(p.236)。
たしかに,虚子の句の「自由自在ぶり」とでも言いたくなるような振れ幅を目の当たりにしていると,それは多少なりとも帰納的であると納得せざるを得ない。そしてそれは,季題から出発するということとも符合することになる。
また,帰納的との指摘が成り立つということは,換言すれば(本書には何も書かれていないし,ここはそれを論じる場でもないが),「虚子以外の俳句のなかには,きわめて演繹的なものがある」ということだ。かなり意訳すると,個別から全体を見ていく帰納的アプローチは,個別のバラつきを容認しながらやがておぼろげに全体が見えてくる,という形をとるのに対して,全体から個別を決めていく演繹的アプローチは,はじめに「俳句とはこういうもの」と決めて,それに合致するように個別を作っていく,という形をとる。
むろん100%帰納法とか100%演繹法という俳人はいないわけで,みなその中間のどこかにいるわけだが,その結果何が起こるかというと,帰納的アプローチは,事物本位で何でも拾っていくので,全体をみたときに時々辻褄が合わなくなったりするのに対して,演繹的アプローチは,自分の理屈にはまる事実しか拾ってこないか,もしくは仕上げの段階で理屈に合わないものを除去するので,ブレはないけどつまらない,ということになるわけだ。無季の句をホトトギス雑詠欄に選び「この句の季題は?」と読者に尋ねられて「誤って無季の句を選びました。抹殺。」と返答する虚子の懐の深さ(『虚子俳句問答 理論編』pp.123-4(2001,角川書店))は,確かに帰納的としかいいようがない。
脱線ついでに無季といえば,「公園の茶屋の亭主の無愛想」という昭和16年4月4日の句(家庭俳句会)は,そのままホトトギス句日記→『句日記』(昭22)→『六百句』(昭和22)まで収録され,後に角川文庫から『五百句・五百五十句・六百句』(昭30)出版の際,ようやく「松の間の桜は幽かなるがよし」という句に差し替えられている(『虚子五句集(上)』p.250(岩波書店,1996))。融通無碍。
他方,自分なりにもう少し調べてみたい点が1点。
「俳諧から俳句への変化に伴い,座の文芸は活字の文芸へ,連衆の文芸は個の文芸へ,存問の文芸は独自の文芸へと変化したが,そうした近代の桎梏から俳句を解き放とうとしたのが虚子の「諷詠」であり,虚子の俳句はしきりに問いかけ,話しかける」という指摘(pp.213-215)は重要である。
その上でさらに「虚子門の俳人には,虚子という選者がいたから,いわば虚子にあてた諷詠に励むことができた。しかし虚子自身は,俳句の読み手としての大衆に対する不信感があり,選者として孤独だった」とされている(pp.222-30)。これはどうなのであろうか。
私たちは,虚子が最晩年まで熱心に句会に出席していたことを知っている。それは単に運動論としてあるいは選者の義務としてではなく,虚子自身が句会を愛好し,句会という形式の歴史とともにあったとさえいえる存在だったからでもある(この点は筑紫磐井「文学における虚子の位置」p.52以下(『俳句』編集部編『高浜虚子の世界』,2009,角川学芸出版)に詳しい)。
そこで考えておかなければならないのは,虚子といえども句会に投句すれば,互選に入ったり入らなかったりするはずだということだ。何が言いたいかというと,句会での互選の具合と,1年後の「ホトトギス」句日記(→単行本「句日記」→「五句集」という過程)との間にはどの程度の相関があったのか,いいかえれば虚子はどの程度互選の結果を考慮していたのか知りたいということ。言い換えれば,句会で「多くの賛同を得た句」とか「スルーされた句」という結果と,翌年の「ホトトギス」に載せる(ひいては「句日記」に載せる)ために選んだ句のあいだには,どの程度の相関があったのだろうということだ。
思いつきの域を出ないのだが,雑詠欄選者としては孤独だったとしても,句会の互選で入ったり入らなかったりの度合が若干でも「ホトトギス」句日記に反映されていれば,まったく孤独とはいえない,という考え方は無理だろうか。やはり句会の会衆も「俳句の読み手としての大衆に対する不信感があり」の内に含まれてしまうのであろうか。
そこで『虚子物語』(清崎敏郎・川崎展宏編,1979,有斐閣)と前掲『虚子俳句の世界』の2冊にあたってみる。選句に臨む虚子の考え方や,虚子選を聴くときの会衆の様子などは書かれているのだが,虚子自らの句が互選でどうなって,それがホトトギス「句日記』にどうつながっていくか,という記述は見当たらないように思われる。従ってこの点は当分,宿題にしておきたい。
2011-08-16 01:01
nice!(1)
コメント(0)
トラックバック(0)


コメント 0