ヒュー・コータッツィ『日英の間で-ヒュー・コータッツィ回顧録-』(松村幸輔訳、日本経済新聞社、1998) [本と雑誌]

自分がイギリスおたくへの道を踏み出したころ、駐日英国大使はコータッツィ氏で、新聞やテレビでその名前を見聞きするたびに、ずいぶんとイギリスっぽくない名前だなあと思っていたものだけど、それから30余年を経て本書を読むと、その名前の由来とともに、当時さまざまな機会に行われていたイギリス関係のイベントのあれこれが背景を伴って説明され、大使自身がそのイベントを開発されたのですね、などと納得することしきり。
回顧録なので登場人物がたくさんいるのだけど、その特徴の第一は、イギリスの人であるか日本の人であるかを問わず、率直な人物評が併記されていること―なかには「史上最低の外相」とか書かれている人もいる―で、これは一つ間違えると上から目線の傲岸な自叙伝になってしまうのだけど、それがそうならないのは、特徴の第二である「まだ知らないことに対する氏の率直な好奇心」が全編にあふれているからである。
戦時中の英国における日本語教育については、大庭定男『戦中ロンドン日本語学校』(中公新書、1988)に詳しいが、イギリス政府は開戦前後にいち早く、日本語のできる者を大量に養成する方針が決定して、1942年5月にはロンドン大学に特別日本語コースが設けられ、政府給費生として集められた17~18歳の学生に対する日本語の特訓が開始されている。余談だが、日本における労使関係論の研究者として著名な―少なくとも労務屋稼業の間では著名な―ロナルド・ドーア氏もこのコースの卒業生である。
で、事実への率直な関心が氏にもたらしたものは大変大きいわけで、占領軍の将校としてやってきたのに温泉旅館を宿舎にしてしまうとか、好奇心由来の型破りなエピソードが山盛り。
吉田茂と直接対等に話をしていた人が存命であること自体がなんだか奇異に感じられるが、それは占領軍の将校という特別な立場がなせる技、つまり若くして日本の上層部と話ができる立場だったから(同年齢の日本人は、ヒエラルキーのずっと下にいたはずだから)で、そういう意味でもこの記録は貴重だ。
(予断だが、昨今妙に脚光を浴びている白洲次郎について「うさんくさい人物」と述べていることも興味深い)
ところで、そのコータッツィ氏が、近年の日本について苦言を呈していることは知られているところである。日本という国を長年見守ってくれて、日本を応援してくださっている(例えば、既に駐日大使を離任されていたにもかかわらず、昭和天皇崩御をめぐるイギリスのタブロイド紙のお下劣な報道に強硬に抗議してくださったことなど)こうした有識者の意見には虚心坦懐に耳を傾け、改めるべき点は静かに改めるべきなのではないかと。
番町句会(12/11) [俳句]
(選句用紙から)
一刷毛の雲を浮べて冬の空
「一刷毛の」といったら秋の雲のように思うのだけど、それがきょうは冬の空にすっと浮かんでいた。空一面の雲とか、塊となってむくむく盛り上がる雲ではなく、すこしかすれた刷毛でさっと描いたような薄雲が、冬の青い空をちょっとしたスピードで動いていく。
餅搗や一臼の他任せたる
季題「餅搗」で冬(12月)。一人で餅をつく人はいないので、親戚かご近所か、いずれにせよ大人数で餅搗をするのだけど、その餅搗の、最初の一臼(餅搗き機でなく、臼と杵で搗いているということですね)だけ加わって、あとはみなさんに「お任せ」したというので、作者はそれなりに年かさの、その場のリーダー格なのだろう。「いや最近腰がどうも…」などというセリフが聞こえてきそう。
(句帳から)
湯豆腐や甚だ頼りなき会話
平野まで迷ひ出でたる冬の雲
短日やばたんと閉まる改札機
里山の地肌の見ゆる冬木立
楮蒸しながら限界集落と
紙漉いて差し込んでくる朝日かな
→紙漉に差し込んでくる朝日かな
一刷毛の雲を浮べて冬の空
「一刷毛の」といったら秋の雲のように思うのだけど、それがきょうは冬の空にすっと浮かんでいた。空一面の雲とか、塊となってむくむく盛り上がる雲ではなく、すこしかすれた刷毛でさっと描いたような薄雲が、冬の青い空をちょっとしたスピードで動いていく。
餅搗や一臼の他任せたる
季題「餅搗」で冬(12月)。一人で餅をつく人はいないので、親戚かご近所か、いずれにせよ大人数で餅搗をするのだけど、その餅搗の、最初の一臼(餅搗き機でなく、臼と杵で搗いているということですね)だけ加わって、あとはみなさんに「お任せ」したというので、作者はそれなりに年かさの、その場のリーダー格なのだろう。「いや最近腰がどうも…」などというセリフが聞こえてきそう。
(句帳から)
湯豆腐や甚だ頼りなき会話
平野まで迷ひ出でたる冬の雲
短日やばたんと閉まる改札機
里山の地肌の見ゆる冬木立
楮蒸しながら限界集落と
紙漉いて差し込んでくる朝日かな
→紙漉に差し込んでくる朝日かな
第92回深夜句会(12/10) [俳句]
今年最後の深夜句会。
(選句用紙から)
ともしびのあたたかさうに枯野かな
季題「枯野」で冬。枯野の中の灯火は、ぽつんと家が建っているのだろうか、それとも枯野の中の道に街灯がともっているのであろうか。「ともしびのあたたかさうに」と言っておいて、でも季題が枯野であるということは、真っ暗ではなく、ある程度枯野の姿が見えているということではないかと。その半面、灯火が暖かそうに見える程度には薄暗いということでもある。
出席者どうしで「この枯野はどのくらいの広さなのか?」「そもそも枯野って、ある程度広くないと枯野とはいわないのでは?」「たとえば100平米ぐらいの空き地は枯野っていわないよね?」「じゃあ何というの?」「冬野でしょ」などと議論が盛り上がる。
海臨む丘の形に大根畑(だいこばた)
季題「大根畑」で冬。上五の「海臨む」がちょっと窮屈な感じは否めない。「海に向く」か、字余りにして「海に臨む」かなあ。急峻な山間地ではなく、海に向かって丘陵がずっと連なった地形なのですね。その丘の形どおりに、緑色のぽつぽつすなわち大根畑が広がっている。海を含めた広がりのある明るい風景。
(句帳から)
庫裏からの咳の聞こゆる読経かな
夕時雨むかし暮らしてゐた町に
赤い実の赤の度が過ぎピラカンサ
(選句用紙から)
ともしびのあたたかさうに枯野かな
季題「枯野」で冬。枯野の中の灯火は、ぽつんと家が建っているのだろうか、それとも枯野の中の道に街灯がともっているのであろうか。「ともしびのあたたかさうに」と言っておいて、でも季題が枯野であるということは、真っ暗ではなく、ある程度枯野の姿が見えているということではないかと。その半面、灯火が暖かそうに見える程度には薄暗いということでもある。
出席者どうしで「この枯野はどのくらいの広さなのか?」「そもそも枯野って、ある程度広くないと枯野とはいわないのでは?」「たとえば100平米ぐらいの空き地は枯野っていわないよね?」「じゃあ何というの?」「冬野でしょ」などと議論が盛り上がる。
海臨む丘の形に大根畑(だいこばた)
季題「大根畑」で冬。上五の「海臨む」がちょっと窮屈な感じは否めない。「海に向く」か、字余りにして「海に臨む」かなあ。急峻な山間地ではなく、海に向かって丘陵がずっと連なった地形なのですね。その丘の形どおりに、緑色のぽつぽつすなわち大根畑が広がっている。海を含めた広がりのある明るい風景。
(句帳から)
庫裏からの咳の聞こゆる読経かな
夕時雨むかし暮らしてゐた町に
赤い実の赤の度が過ぎピラカンサ
番町句会(11/13) [俳句]
4か月ぶりの番町句会。締切前に亥の子餅(=季題である)をいただく。
きょうのお題は「時雨」。

(選句用紙から)
朝のカフェ十一月の香りして
いろいろな鑑賞ができるが、通りに面した窓際の席とか、あるいは外に設けられた席と考えると面白いかもしれない。コーヒーの香りとかエスプレッソマシンの音自体は一年中そこにあるのだとしても、それをとりまく町の音や人の姿、空気の冷たさは日々違っているのですね。十一月のよく晴れた朝、冷たい風と明るい光のなかでコーヒーや紅茶をいただく気分が全部合わさったものが「十一月の香り」なのだろう。
酉の市熊手買ふ店替へてみる
すこし哀しく、詩情あふれる一句。酉の市には縁起ものの熊手を売る露店が連なっている。作者は毎年その神社に詣でて、酉の市の同じ露店で熊手を買っていたのだろう。今年も酉の市へやってきて、さていつもの店で買おうと足を向けかけたのだけど、しかし、ことし一年あまりよいことがなかったのであろう、ふと、違う露店で買ってみようかと思い直したというのである。買う店を替えたところで、それがどうという話でもないことは自分でもわかっているのだけど、でもそんなちょっとした気分に、酉の市の雑踏と、年末をすぐ後に控えた一年間の思いというようなものが凝縮されていて、でもベタベタしていない。
(句帳から)
帳簿やらコピーやらあり風邪薬
亥の子餅楕円形して同じ向き
村外れまで追つてくる時雨かな
きょうのお題は「時雨」。

(選句用紙から)
朝のカフェ十一月の香りして
いろいろな鑑賞ができるが、通りに面した窓際の席とか、あるいは外に設けられた席と考えると面白いかもしれない。コーヒーの香りとかエスプレッソマシンの音自体は一年中そこにあるのだとしても、それをとりまく町の音や人の姿、空気の冷たさは日々違っているのですね。十一月のよく晴れた朝、冷たい風と明るい光のなかでコーヒーや紅茶をいただく気分が全部合わさったものが「十一月の香り」なのだろう。
酉の市熊手買ふ店替へてみる
すこし哀しく、詩情あふれる一句。酉の市には縁起ものの熊手を売る露店が連なっている。作者は毎年その神社に詣でて、酉の市の同じ露店で熊手を買っていたのだろう。今年も酉の市へやってきて、さていつもの店で買おうと足を向けかけたのだけど、しかし、ことし一年あまりよいことがなかったのであろう、ふと、違う露店で買ってみようかと思い直したというのである。買う店を替えたところで、それがどうという話でもないことは自分でもわかっているのだけど、でもそんなちょっとした気分に、酉の市の雑踏と、年末をすぐ後に控えた一年間の思いというようなものが凝縮されていて、でもベタベタしていない。
(句帳から)
帳簿やらコピーやらあり風邪薬
亥の子餅楕円形して同じ向き
村外れまで追つてくる時雨かな
森枝卓士「カレーライスと日本人」(講談社学術文庫、2015) [本と雑誌]
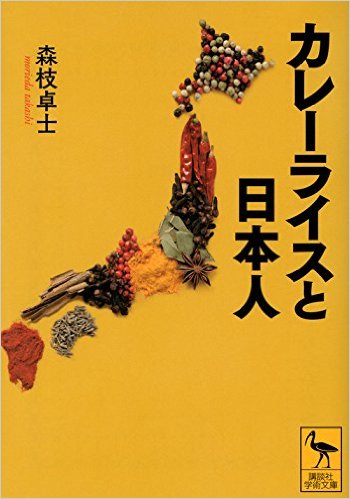
面白い。
家庭だろうと町の食堂だろうと社食だろうと、日常的に私たちが親しんでいるカレーが、どのようにしてインドから日本までやってきて、日本でどのように取り入れられて定着したのかを丹念に追いかけていく。イギリスでカレー粉が誕生したいきさつを追究するため、大英図書館でさまざまな一次史料(なかには初代ベンガル総督ヘイスティングスの手紙なんていうものもある)を探し、ついには、イギリスの文献に初めてカレーが現れるのは、これまでの通説よりずっと早い1747年であることまで発見してしまう。
また、日本の社会にカレーが広く普及した理由は、それがインド料理でなくイギリス伝来の西洋料理(洋食)と受け止められていたからだ、という指摘(pp.210-12)は重要。この視点で考えると、ペルー料理でもモロッコ料理でもおいしくいただいてしまう現在の世相は、最近に至ってようやくそういうしばりが緩くなった結果ということになるのだろうか。
松本楼の話や中村屋の話も出てくるが、あの店がおいしいとかこの店はどうだとかいう本ではない。これだけ毎日のように食べているのに、その受容過程がほとんど知られていないことも不思議だが、それを明らかにしていく過程も、またドキュメンタリー番組を見ているような面白さがあった。それは、調べ物をお仕事として義務的にこなすのでなく、「知らないこと」を掘り下げてみたいという明快な好奇心が著者にあるからで、偏見をもたず虚心坦懐にずんずん分け入っていくその姿勢が、読者の共感につながるのだと思う。

