レベッカ・ソルニット 『ウォークス 歩くことの精神史』(東辻賢治郎訳、左右社、2017)【一部ネタバレ注意】 [本と雑誌]
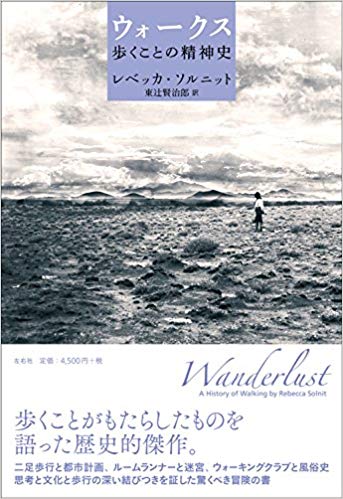
バックパッカーで、俳句が好きで、ロングトレイルを歩いたり100キロウォークに出場したりする人間にとって、こういう本は必修科目といってもよい。歩くことが体にいいとか悪いとかの効能の話ではなく(そういうhow to本のなんと多いこと!)、「歩くことはなぜ楽しいのか?」という根本的な疑問に、いくつかの楽しい仮説を提供してくれる一冊。
原題「wanderlust -- a history of walking」の「wanderlust」は、「旅行熱、放浪癖」といった意味なので、邦題の「精神史」は少々意訳気味。
本文だけで500ページを超えているが、歩くこと(正確にいえば、歩くこと自体を目的として、歩くこと)が、芸術の歴史上、あるいは社会史的にどう取り扱われてきたかが時代を追って説明されており、少しずつ読み進めればそれほど理解困難ではない。個別に「へぇ」と思った点をいくつか。
・巡礼の根底にあるのは、聖なるものはまったくの非物質的存在ではなく、霊性には地理があるという考えだ…巡礼は信ずることと動くこと、思惟と行為をむすびあわせる。聖なる存在が物質性と場所を備える、ということがこの調和の条件となるのはまことに理の通ったことだ。(p.86)
巡礼へとおもむくとき、人は世界との係累――家族、愛するもの、地位、あれこれの義務――を置き去りにし、歩く群れのひとりとなる。成就したことと捧げたものを除いては、巡礼者たちを隔てるものはない。(p.88)
・今日の読者にとっては、絵のような眺め、あるいは景色のための観光といったものの存在は、風景を好むこととおなじようにそれほど特筆すべきものとは思われないかもしれない。しかし、そのすべては十八世紀に発明されたものなのだ。(p.157)
・十九世紀における歩行の文芸の主流が歩くことのエッセイという形式だったとすれば、に十世紀にはきわめて長い距離を歩くことについての長々とした物語がそれに代わる。…わたしの知るかぎり、歩くこと自体を目的にした長距離の徒歩旅行について述べた最初の重要な文章は、ジョン・ミューアの『1000マイルの歩み』だ。一八六七年のインディアナポリスからフロリダ・キーズまでの旅が記されている。(pp.207-8)
・日本では、山は有史以前から宗教的に重要な存在だった…後になると、山に登ることが宗教行為の中核を占めるようになった。登山を特徴にした仏教宗派といえる修験道がそのことをはっきり示している…修験道は十九世紀後期に禁止され日本の宗教ではなくなるが、寺社や行者が消えることはなく、富士山はメジャーな巡礼地でありつづけ、日本人はいまなお世界的にももっとも熱心に山に登っている。(pp.240-1)
・わたしが出会ったイギリス人の多くは、土地の景観は彼らの受け継いだ遺産であり、自分たちにはその場に足を運ぶ権利があるという感覚をもっていた。合衆国ではそれよりはるかに私有財産が絶対視され、その正当化に寄与する存在として莫大な公有地がある。(p.270)
・しだいに周囲の風景との区別を失っていくうちに、庭はその必要性をも失っていたのだ。(p.151)
・田舎歩きの歴史が抱える大いなる皮肉、あるいは詩的な正義といえるのは、上流階級の庭園からはじまった嗜好が、巡りめぐって私的所有を絶対的にして特別の権利として攻撃するに至ったことだ。(p.277)
この本のなかにもフレッチャーの「遊歩大全」が出てくるが、読み終えて感じたのは、この「歩くことの精神史」が、「遊歩大全」の後継者(後継書?)だということ。
もうひとつ、自分が長いあいだ、旅するときに意識していた「地面の上を連続して移動する感覚」について、この本が同様の指摘をしてくれたことが嬉しかった。先に自分の持論を紹介しておくと、それはこのようなことだ。
自分の家から駅までの道順を思い描くとき、途中にある目標物、すなわち、大きな冠木門のある家とか、個人タクシーの営業所とか小さな喫茶店とか、パン屋とかスーパーとか、そうしたものが順番に配置されて、そのあとで駅に着く。それは、「頭の中の地図」に、それらの目標物が順番に(sequentialに)プロットされているからだ。駅で電車に乗って、大きなターミナル駅まで行くときにも、一軒一軒の家はわからないにしても、途中の駅は、頭の中の地図に従って順番に現れる。
ところが、飛行機で北米や欧州のどこかへ行くとき、そうした「頭の中の地図」の連続性はまったく失われてしまう。飛行機のドアが閉まってから、現地でもう一度開くまで、地図は空白なのだ。
で、この本ではこの点について以下のように説明している。
・わたしたちの知覚はそれ以来も加速されつづけているが、当時にすれば列車の速度は目も眩むものだった。それ以前の陸上移動の方法は旅人と環境を親密な関係でむすぶものだったが、十九世紀の精神にとって鉄道の速度は速すぎ、視界を掠めて飛んでゆく樹々や丘陵や町並みと視覚的な関係をむすぶことは不可能だった。此方と彼方との間にひろがる地表ととりむすんでいた空間的・感覚的な関係は希薄なものとなってゆく。その代わりに、二つの地点を隔てるものは時間だけとなり、それも留まることなく節減されてゆく。(p.432)
・近代以降の空間・時間・身体性の喪失に抗って歩きつづける者がいれば、それは対抗文化(カウンターカルチャー)あるいは副次文化(サブカルチャー)ということになるだろう。(p.447)
そうでしょうそうでしょう。こんな話をどっさり仕込んでから道を歩くと、それが駅から家までの道であっても、これまでより少し楽しくなるから不思議。
2020-03-09 00:27
nice!(0)
コメント(0)


コメント 0