ジュリー・オオツカ『屋根裏の仏さま』(岩本正恵・小竹由美子訳、新潮社、2016) [本と雑誌]
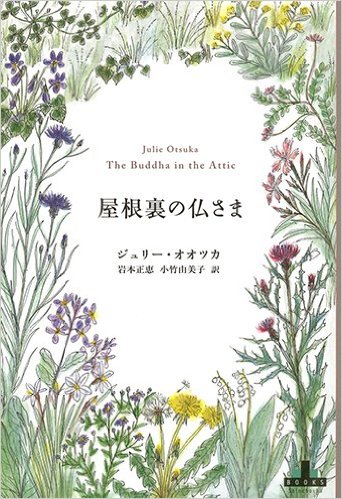
数ページ読む。読むのがつらくなって閉じる。しかし数分すると読まずにいられなくなり、また手にとる。
この繰り返しで、およそ150ページを読むのに2日かかる。
20世紀前半の一時期、海を渡って在外邦人にとついだ「写真花嫁」の物語が群像として描かれるのだけど、彼女たちは冒頭からさまざまな災厄にみまわれて次々に命を落としていく。ひとつひとつのエピソードは具体的かつ簡潔で、著者が丹念に取材をしたのだろうと思われる。それでも現地で子どもを産み、育て、ある者は安定した生活を得るのだけど、そこへ戦争がやってきて、ふたたび何もかも破壊される。126ページから10ページ以上にわたって続く「どのように去っていったか」の繰り返しは圧倒的な迫力。
この本を特徴づけることとして、まず、一人ひとりを美化しない、つまり悲劇のヒロインに仕立てようとしないことがある。彼女たちにせよ、自分たちにせよ、自らの身勝手さや、その時代の偏見から誰も逃れられない。それがかえって、リアリティをもたらしている。
また、相反するできごとやことがらが頻繁に語られ、人の心の難しさや不条理さを読み手に感じさせる。
たとえば、「日本に残してきた三歳の娘が、死ぬまで忘れられずにいる」のに、何十年も暮らしてきた地域のひとびとからは、1年も経たないうちに忘れられてしまう。
また、必死な思いで娘や息子を育て、教育を受けさせたのに、教育を受けたその子は、親のみすぼらしい服や、かまどの神様に手を合わせる習慣を見て恥じたり笑ったりする。
このアイロニーは切ない。
本文を読み終えたあと、訳者あとがきの最後の数行で、訳者(たち)にも「もうひとつの物語」があったことを知る。この尊いリレーがあって、自分はこの本が読めたのかと思うと頭がさがる。
本書は小説でもあり、ドキュメンタリーでもあるのだけど(いゃ、もちろん小説なのだけど)、言葉のリズムがそうさせるのか、なにか長編の詩を読んでいるような錯覚を覚える。
そして、読みおえた後も長くつづく余韻。まだ6月だが、今年のベスト1はこれで確定かもしれない。
2016-07-15 00:02
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)


コメント 0